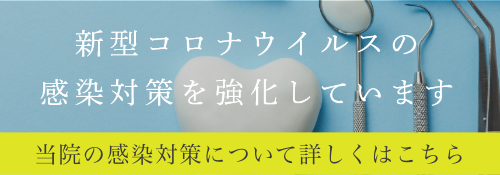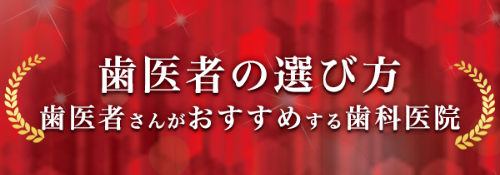歯周病とは?

歯周病は初期症状が分かりにくい「静かなる病気」
歯周病は「静かなる病気(サイレントディジーズ)」と呼ばれ、その名の通り、初期症状がほとんど自覚できないのが特徴です。むしろ気づいた時にはかなり進行している場合が多く、歯を支える歯ぐきや骨が大きく損なわれていることもあります。
初期段階では歯ぐきの腫れや出血などが見られる場合がありますが、痛みを感じることは稀です。このため、多くの方が「大丈夫だろう」と放置してしまい、結果として病状が進行してしまうのです。
日本人の約8割がかかると言われる病気の現状
日本人成人の約8割が歯周病にかかっている、またはそのリスクがあると言われています。特に30代以降から発症率が急激に高まります。オフィスワークで座りがちな生活や、不規則な食事、睡眠不足などがリスクを高める要因となることも。忙しいライフスタイルが影響し、ケアがおろそかになりがちな方は注意が必要です。
歯周病は、仕事のパフォーマンスにも影響を与える可能性があります。歯ぐきの炎症による不快感や痛みはもちろん、進行すると噛む力が低下し、食事を楽しむことが難しくなることも。さらに、口臭が強くなることで職場での対人関係に影響を与えることも考えられます。
放置すると歯を失うだけでなく、全身の健康にも影響が
歯周病は、お口の中だけの問題にとどまりません。近年の研究では、歯周病が全身の健康に与える悪影響が明らかになっています。歯周病菌や炎症性物質が血液を通じて全身に広がり、以下のような疾患のリスクを高める可能性があります:
・糖尿病:歯周病が進行すると、血糖値のコントロールが難しくなることが分かっています。
・心疾患・脳梗塞:歯周病菌が血管に悪影響を及ぼし、動脈硬化を引き起こす可能性があります。
・誤嚥性肺炎:特に高齢者において、歯周病菌が肺に入り込み炎症を引き起こすリスクがあります。
オフィスワーカーは座りっぱなしの生活や運動不足が原因で全身の血流が滞りがちです。このような生活習慣が歯周病と全身疾患のリスクを高める可能性があるため、早めの対策が必要です。
忙しい日々でも歯周病予防を始めよう
このように、歯周病は「ただの歯ぐきの病気」ではなく、放置すると全身に影響を及ぼす可能性のある重大な疾患です。しかし、適切な予防と早期治療を行えば進行を食い止めることができます。毎日の正しいブラッシングやデンタルフロスの活用に加え、定期的な歯科検診を受けることが大切です。
歯周病は気づいたその時から対策を始めることができます。少しでも歯ぐきの腫れや出血が気になる場合は、ぜひ歯科医院に相談してください。あなたの歯と全身の健康を守るため、歯周病のケアを始めてみませんか?
なりやすい人の特徴① ~お口のケアが不十分~

歯周病は、毎日のケアが十分でないことが最も大きな原因の一つです。お口の健康を維持するためには、正しい方法でのケアが欠かせません。しかし、多くの人が適切なケアを行えていないため、知らず知らずのうちに歯周病のリスクを高めています。以下では、お口のケアが不十分な具体的な例とその影響について解説します。
正しいブラッシング方法が身についていない人
歯周病予防の基本は、毎日のブラッシングです。しかし、適切な方法で磨けていない場合、歯垢(プラーク)が歯と歯ぐきの間にたまり、歯周病菌が増殖してしまいます。
よくある問題点
・磨き残しが多い
・力を入れすぎて歯ぐきを傷つけてしまう
・歯ブラシの毛先が届きにくい奥歯や歯間を十分に清掃できていない
改善のポイント
・45度のブラッシング角度:歯ブラシを歯ぐきに対して45度の角度で当て、細かく動かします(バス法)。
・適切な歯ブラシ選び:歯ぐきに優しい柔らかめのブラシを使用する。
・電動歯ブラシの活用:短時間で効率的な清掃が可能になります。
デンタルフロスや歯間ブラシを使用していない人
歯ブラシだけでは、歯と歯の間にたまった汚れを完全に除去することは困難です。この隙間に蓄積された歯垢が、歯周病の原因となる細菌の温床になります。
デンタルフロスや歯間ブラシは、この部分の清掃に欠かせないアイテムです。しかし、これらを日常的に使用している人は少なく、特に歯間の清掃が不十分だと、歯周病のリスクが高まります。
フロスや歯間ブラシの使い方に慣れていない場合は、歯科医院で適切な方法を指導してもらうことで効果的なケアが可能です。
定期的な歯科検診を受けていない人
歯周病は、初期段階では痛みや目立った症状がほとんどありません。そのため、自己判断で「問題ない」と考えてしまい、定期的な歯科検診を怠る方が多く見られます。
歯科検診では、歯周病の早期発見や予防ケアを行うことができます。また、歯石の除去や歯周ポケットのクリーニングなど、プロフェッショナルなケアによって病気の進行を抑えることが可能です。
検診を受けないまま症状が進行すると、歯ぐきの腫れや出血、歯の動揺などが現れ、治療に時間と費用がかかることも少なくありません。定期的な受診が、健康な歯ぐきを保つ最善策です。
忙しいオフィスワーカーにおすすめのケア習慣
オフィスワーカーの方々は、日々の忙しさから口腔ケアを後回しにしてしまうことが多いかもしれません。しかし、小さな習慣を取り入れるだけで、歯周病予防の効果を大幅に高めることができます。
1.歯ブラシとデンタルフロスをオフィスに常備
ランチ後に簡単なケアをするだけでも効果的。
2.短時間でできるケアを取り入れる
忙しい日でも夜だけは丁寧なブラッシングを意識する。
3.定期検診をカレンダーに記載
スケジュールに組み込むことで受診を忘れにくくなります。
なりやすい人の特徴② ~生活習慣がリスクを高める~

歯周病はお口の中だけの問題ではなく、日々の生活習慣が大きな影響を与える病気です。特に、現代社会で忙しい日々を送るオフィスワーカーにとって、生活習慣が乱れることは珍しくありません。喫煙、ストレス、不規則な生活習慣は歯ぐきの健康に悪影響を及ぼし、歯周病のリスクを大幅に高める要因となります。ここでは、生活習慣と歯周病の関係を詳しく解説します。
喫煙者は非喫煙者に比べ歯周病のリスクが約5倍に
タバコが健康に悪影響を及ぼすことは広く知られていますが、歯周病へのリスクも見逃せません。喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病にかかるリスクが約5倍高いと言われています。その理由は、喫煙が歯ぐきの血流を悪化させ、免疫力を低下させるからです。
喫煙によって歯ぐきの血管が収縮し、炎症が進行しても目立った腫れや出血が見られない場合があります。これにより、歯周病が進行していることに気づかないケースが多く、治療が遅れる要因となります。また、タバコに含まれる有害物質が歯ぐきの組織再生を妨げるため、治療効果が出にくいことも特徴です。
禁煙することで、歯周病リスクが減少するだけでなく、治療後の経過が良くなることが分かっています。禁煙は、歯周病予防の第一歩として重要な選択です。
ストレスが多い生活が免疫力を低下させる
現代社会で避けられないストレスも、歯周病のリスクを高める要因の一つです。ストレスが増加すると、体内でコルチゾールというホルモンが分泌されます。このホルモンは一時的に体を守る役割を果たしますが、過剰に分泌されると免疫機能を抑制してしまいます。
免疫力が低下すると、歯周病菌に対する体の防御機能が弱まり、炎症が悪化しやすくなります。また、ストレスが原因で歯ぎしりや食いしばりが起こることもあります。これらの習慣は歯や歯ぐきに負担をかけ、歯周病の進行を加速させる要因となります。
ストレスを軽減するためには、適度な運動や趣味の時間を持つこと、リラックスできる時間を確保することが重要です。心と体の健康を整えることが、歯周病予防にもつながります。
睡眠不足や不規則な食事が歯ぐきの健康に悪影響
睡眠不足や不規則な食事も、歯周病のリスクを高める大きな要因です。睡眠は、体の回復と免疫力の維持に欠かせないものです。睡眠時間が不足すると、免疫システムが正常に働かなくなり、歯周病菌に対する抵抗力が弱まります。
さらに、不規則な食事や栄養バランスの偏りも歯ぐきの健康に悪影響を及ぼします。特にビタミンCやカルシウムなどの栄養素が不足すると、歯ぐきの組織が弱くなり、炎症を起こしやすくなります。また、糖分の多い食事は、歯周病菌の増殖を促進するため注意が必要です。
規則正しい生活習慣を意識し、栄養バランスの取れた食事と十分な睡眠を確保することで、歯周病リスクを低減できます。
生活習慣を見直して歯周病を予防しよう
生活習慣は、歯周病の発症や進行に密接に関連しています。喫煙やストレス、睡眠不足、不規則な食事などが重なると、歯ぐきの健康が損なわれ、歯周病が進行しやすくなります。以下の対策を日常生活に取り入れてみましょう:
・禁煙を決意し、歯ぐきの血流を改善する
・ストレス管理を心がけ、リラックスできる時間を持つ
・十分な睡眠とバランスの取れた食生活を意識する
これらを実践することで、歯周病だけでなく、全身の健康も向上します。生活習慣の改善は難しいと感じるかもしれませんが、小さな一歩から始めることで、長期的に健康な歯ぐきを保つことができます。歯周病予防のために、ぜひ生活習慣を見直してみてください。
なりやすい人の特徴③ ~全身疾患との関係~

歯周病はお口の中だけの問題ではなく、全身疾患と密接に関係していることが近年の研究で明らかになっています。糖尿病や骨粗鬆症、高血圧、心疾患といった疾患を持つ人は、歯周病のリスクが高まることが知られています。また、歯周病がこれらの疾患を悪化させることも報告されており、予防と管理が重要です。以下では、それぞれの関係性を詳しく解説します。
糖尿病と歯周病の相互関係:悪化するとどちらも進行
糖尿病と歯周病は「双方向の関係」にあることが分かっています。糖尿病の人は、そうでない人に比べて歯周病になりやすく、またその進行も早いとされています。その原因は、血糖値が高い状態が続くことで免疫機能が低下し、歯周病菌に対する抵抗力が弱まるためです。さらに、高血糖は歯ぐきや歯槽骨の修復能力を妨げるため、炎症が悪化しやすくなります。
一方で、進行した歯周病は、炎症性物質が血中に入り、血糖値のコントロールを難しくします。歯周病治療によって糖尿病の管理状態が改善することが示されており、定期的な歯科ケアは糖尿病患者にとって不可欠です。
骨粗鬆症による歯槽骨の弱化
骨粗鬆症は、骨密度が低下して骨がもろくなる病気で、特に閉経後の女性に多く見られます。この病気は歯を支える歯槽骨にも影響を及ぼします。骨粗鬆症が進行すると、歯槽骨が弱くなり、歯周病のリスクが高まるとともに、進行が加速する可能性があります。
また、骨粗鬆症の治療に使用される一部の薬剤(ビスフォスフォネート製剤)には、歯周病治療後の回復を妨げる副作用が報告される場合があります。そのため、歯周病治療を行う際には、事前に歯科医と全身の健康状態を共有することが大切です。
高血圧や心疾患など生活習慣病との関連
高血圧や心疾患などの生活習慣病とも歯周病は深く関係しています。歯周病菌が引き起こす炎症性物質は、血管を硬化させたり、動脈硬化を促進させる可能性があるとされています。これにより、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まることが懸念されています。
さらに、慢性的な歯周病が持続することで全身の炎症状態が続き、高血圧の悪化につながるケースもあります。こうした背景から、歯周病治療は心血管疾患のリスクを軽減するためにも重要です。
歯周病予防と全身疾患管理の両立が重要
歯周病が全身疾患に与える影響を最小限に抑えるためには、以下のポイントを意識することが大切です:
・定期的な歯科検診:歯周病の早期発見と治療を行い、全身への影響を防ぐ
・生活習慣の改善:バランスの取れた食事や適度な運動で全身の健康を維持する
・疾患管理:糖尿病や高血圧などの基礎疾患を適切に管理し、全身とお口の健康を両立させる
歯周病は全身疾患と密接に関係しているため、予防と管理が重要です。少しでも歯ぐきの異常を感じた場合は、早めに歯科医院を受診し、適切なケアを受けましょう。
なりやすい人の特徴④ ~ホルモンバランスの影響~

歯周病は、日々のケアや生活習慣だけでなく、体内で起こるホルモンバランスの変化によっても大きな影響を受けます。特に女性は、妊娠、思春期、更年期、月経周期など、ライフステージごとにホルモンの変動が起こるため、歯ぐきの状態が変化しやすいと言われています。以下では、ホルモンバランスが歯周病にどのような影響を与えるのか、具体的に解説します。
妊娠中に起こる歯ぐきの変化
妊娠中は、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンの分泌が増加します。このホルモンの変化は、歯ぐきに炎症を起こしやすい環境を作り、「妊娠性歯肉炎」と呼ばれる状態を引き起こします。
妊娠性歯肉炎は、歯ぐきの腫れや出血を伴うことが多く、放置すると歯周病へと進行するリスクがあります。また、重度の歯周病は早産や低体重児出産のリスクを高めることも知られています。
妊娠中は体調の変化が多く、歯科受診をためらう方もいらっしゃいますが、この時期に適切なケアを行うことで、母体と胎児の健康を守ることができます。妊娠が分かったら、歯科検診を受け、専門家に相談することをおすすめします。
思春期や更年期によるホルモン変動
思春期にはホルモン分泌が活発化し、歯ぐきが一時的に腫れやすくなる場合があります。この時期に適切な口腔ケアを行わないと、歯ぐきに炎症が生じやすく、歯周病のリスクが高まります。また、この時期にケアを怠ると、将来的な歯ぐきの健康に影響を与える可能性があります。
一方、更年期においては、エストロゲンの分泌が急激に減少します。この変化は、骨密度の低下だけでなく、歯槽骨の弱化にもつながります。その結果、歯周病が進行しやすくなるだけでなく、治療の経過にも影響を与える場合があります。
月経周期と歯ぐきの炎症
女性の月経周期も、歯ぐきの状態に影響を与えることがあります。生理前や生理中にホルモンの変化が起こり、歯ぐきが一時的に腫れたり、出血しやすくなることがあります。このような変化は通常、月経が終わると改善されますが、定期的に炎症が繰り返されると、歯周病のリスクが高まる可能性があります。
特に月経中に歯ぐきの異常を感じた場合は、デンタルフロスや歯間ブラシを活用し、口腔内を清潔に保つことが大切です。また、歯科医院での定期的なメンテナンスを受けることで、歯周病の進行を防ぐことができます。
ホルモンバランスの変化と歯周病予防
女性がライフステージで経験するホルモンバランスの変化は避けられないものですが、適切なケアを行うことで歯周病のリスクを大幅に減らすことができます。以下のポイントを実践してみてください:
・ライフステージに応じた定期検診:妊娠中、思春期、更年期などの時期に合わせて歯科検診を受ける
・毎日の口腔ケア:正しいブラッシングと補助用具の活用で、歯ぐきの健康を維持
・専門家への相談:歯ぐきの状態が気になる場合は、早めに歯科医院で相談する
ホルモンバランスの変化がある時期こそ、お口の健康を守るための重要なタイミングです。
歯周病になりにくい人の共通点

歯周病を予防し、生涯健康な歯と歯ぐきを維持するためには、日々の生活習慣が重要な役割を果たします。歯周病になりにくい人たちは共通して、オーラルケアや生活習慣の基本をしっかりと守っています。ここでは、歯周病を遠ざけるための具体的なポイントを詳しく解説します。
毎日の正しいオーラルケアを欠かさない
歯周病予防の基本は、毎日の正しい歯磨きです。ただ磨くだけでなく、歯と歯ぐきの境目(歯肉溝)にたまったプラークをしっかり取り除くことが重要です。適切なブラッシング方法としては「バス法」が推奨され、歯ブラシの毛先を歯ぐきに対して45度の角度で当て、軽い力で小刻みに動かします。
また、歯ブラシだけではなく、デンタルフロスや歯間ブラシを使うことで歯と歯の間にたまった汚れを除去できます。特に歯周病になりにくい人は、こうした補助用具を日常的に使用し、口腔内を清潔に保つ努力を怠りません。
定期的に歯科医院でメンテナンスを受けている
歯周病になりにくい人の多くは、歯科医院での定期検診を欠かしません。歯科検診では、自分では気づきにくい歯周病の初期症状や歯石の蓄積をチェックできます。歯石は自宅でのケアでは除去できないため、歯科医院でのプロフェッショナルケアが欠かせません。
さらに、定期検診では歯ぐきの状態を評価する「歯周ポケット検査」や、歯石除去(スケーリング)、歯ぐきの深い部分までクリーニングする「ルートプレーニング」などが行われます。これにより、歯周病の進行を未然に防ぐことが可能です。
理想的な検診頻度は3~6ヶ月に1回です。昼休みや出勤前、退勤後に通える歯科医院を探すことで、時間を有効活用することをお勧めします。
定期的なメンテナンスを受けることで、仕事中の集中力や体調管理にも好影響を与えます。
バランスの取れた食生活と規則正しい生活習慣
歯周病予防には、食生活やライフスタイルの改善も重要な要素です。特に、デスクワークが中心のオフィスワーカーは、不規則な食事や運動不足が歯ぐきの健康に影響を与えることがあります。
◎健康的な食生活のポイント
・ビタミンCを摂取:柑橘類やピーマンに含まれるビタミンCは、歯ぐきの血管を強化し、炎症を抑えます。
・カルシウムを意識:乳製品や小魚、緑黄色野菜を摂ることで、歯を支える骨を健康に保ちます。
・糖分を控える:スナック菓子や甘い飲み物は、歯周病菌のエサとなるため控えましょう。
◎規則正しい生活習慣のポイント
・睡眠時間を十分に確保することで免疫力を高める。
・ストレスを軽減するために、仕事中に短時間のリフレッシュタイムを設ける。
・オフィス内で軽いストレッチやウォーキングを取り入れ、血流を促進する。
歯周病になりにくい人の習慣を取り入れよう
歯周病を防ぐためには、以下のポイントを日常生活に取り入れることが効果的です:
1.毎日のブラッシングを見直し、デンタルフロスや歯間ブラシを活用する
2.3~6ヶ月ごとに歯科医院で定期検診を受ける
3.ビタミンやミネラルをバランスよく摂取し、糖分を控えた食生活を心がける
4.規則正しい生活習慣とストレス管理を徹底する
これらを意識することで、歯周病だけでなく、全身の健康を守ることができます。「歯周病にならないための習慣」を今日から取り入れ、健康な口腔環境を目指しましょう。
セルフチェックで分かるリスク

歯周病は「サイレントディジーズ(静かなる病気)」とも呼ばれ、初期段階では症状が目立たず、自覚が難しいことが特徴です。しかし、進行すると歯を失う原因になるだけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、早期発見と予防が非常に重要です。ここでは、自宅やオフィスでも簡単にできるセルフチェックのポイントをご紹介します。
歯ぐきが赤く腫れている、ブラッシングで出血がある
健康な歯ぐきは、ピンク色で引き締まった状態です。しかし、歯周病の初期症状として、歯ぐきが赤く腫れたり、ブラッシング時に出血することがあります。これは、歯周病菌による炎症が歯ぐきにダメージを与えているサインです。
出血がある場合でも痛みを感じないことが多く、「たまたま出血しただけ」と見過ごされることがあります。こうした症状が続く場合は、早期の治療が必要です。軽度のうちに治療を開始すれば、進行を抑えることが可能です。
朝起きたときに口の中がネバネバする
歯周病が進行すると、歯周ポケット(歯と歯ぐきの間の溝)に歯垢や歯石がたまり、歯周病菌が増殖します。この結果、口の中がネバネバとした不快感を感じることがあります。特に朝起きたときにこの症状が強く感じられる場合は、歯周病が進行している可能性が高いです。
さらに、歯周病菌の活動によって発生するガスが原因で、口臭が強くなることもあります。歯周病が原因の口臭は、一般的な口臭ケア製品では改善が難しく、専門的な治療が必要です。
歯が浮いたような感覚や歯ぐきの下がりを感じる
歯周病が中期から後期に進行すると、歯を支える歯槽骨が溶けてしまい、歯が浮いたような感覚が生じることがあります。また、歯ぐきが下がり、歯が長く見えることも歯周病の特徴的な症状です。
歯ぐきが下がると、歯の根元が露出し、冷たいものや甘いものがしみるようになります。この状態を放置すると、さらに歯槽骨が破壊され、最終的に歯が抜け落ちてしまうこともあります。
オフィスワーカーがセルフチェックを日常に取り入れる方法
以下のセルフチェックリストで、ご自身の歯ぐきの状態を確認してみましょう:
・ランチ後のケアを活用
ランチ後に歯磨きをする際、歯ぐきの色や出血の有無を確認。
・朝の習慣にプラス
朝起きたときのネバネバ感や口臭を意識し、気になる場合はメモしておく。
・定期的に鏡で確認
歯ぐきの状態を週に1回チェックする習慣をつける。
このような症状が1つでも当てはまる場合、歯周病の可能性があります。セルフチェックはあくまで目安ですが、早めに歯科医院を受診することで、進行を抑えたり、症状を改善することができます。
日常生活でできる予防法
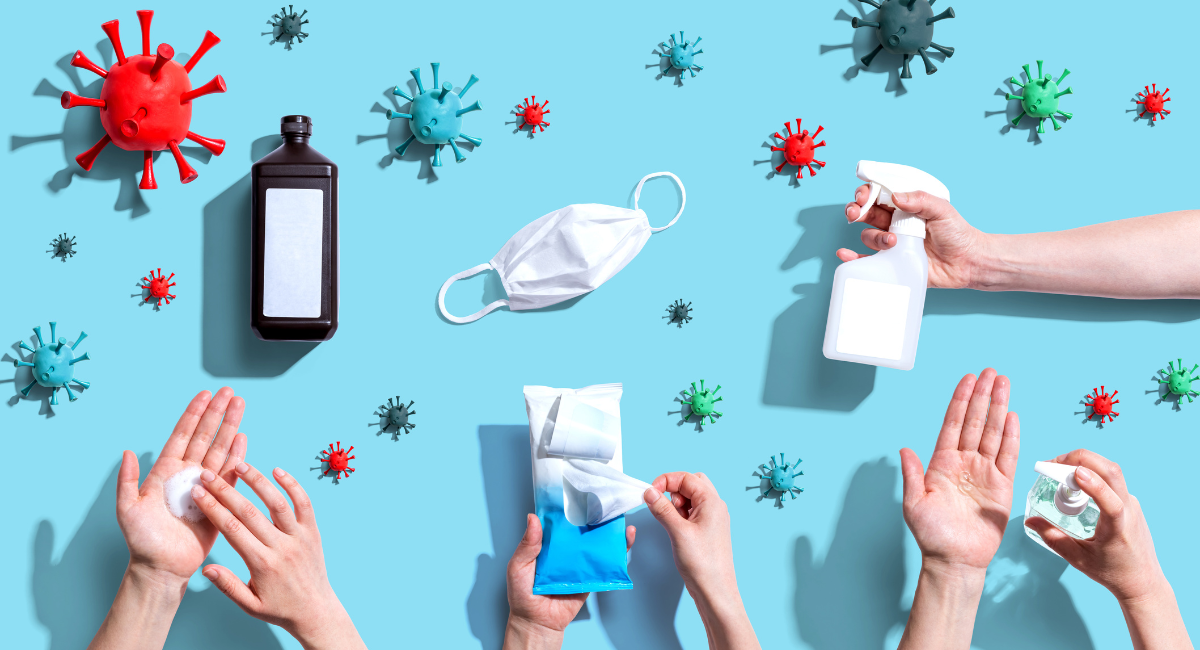
歯周病は、日々の生活習慣の改善によって予防することができます。進行してから治療を行うよりも、日常的なケアを取り入れることで、健康な歯ぐきを維持し、全身の健康にも良い影響を与えることが可能です。以下では、具体的な予防法について解説します。今日から始められる習慣を取り入れて、歯周病のリスクを減らしましょう。
正しいブラッシング方法と補助用具の使い方
毎日の歯磨きは、歯周病予防の基本です。しかし、適切なブラッシング方法を知らないと、効果的に歯垢を除去することができません。特に歯と歯ぐきの境目(歯肉溝)は歯垢がたまりやすい場所であり、重点的にケアする必要があります。
おすすめのブラッシング方法
・バス法:歯ブラシの毛先を歯ぐきに対して45度の角度で当て、軽い力で小刻みに動かします。この方法は、歯肉溝の清掃に効果的です。
・時間をかける:1日2回、少なくとも2~3分かけて丁寧に磨きましょう。
また、歯ブラシだけでは歯と歯の間の歯垢を完全に除去することはできません。デンタルフロスや歯間ブラシを使用することで、歯周病菌の温床となる歯間部を清潔に保つことができます。特に歯間ブラシは、歯と歯の隙間が広い方に適しており、デンタルフロスと使い分けると効果的です。
喫煙やストレスのコントロール
喫煙は、歯周病の最大のリスク因子の一つです。タバコに含まれる有害物質は歯ぐきの血流を阻害し、免疫力を低下させるため、歯周病が進行しやすくなります。また、歯ぐきの腫れや出血といった初期症状が隠れることがあり、気づかないうちに悪化するケースもあります。禁煙は、歯周病予防のために欠かせない重要なステップです。
さらに、ストレスも免疫機能を低下させ、歯周病の進行を促進する要因となります。ストレスによって引き起こされる歯ぎしりや食いしばりは、歯と歯ぐきに大きな負担をかけ、症状を悪化させる可能性があります。適度な運動や趣味の時間を持ち、リラクゼーションを取り入れることで、ストレスを軽減しましょう。
歯科医院でのプロフェッショナルケアの重要性
自宅でのケアに加え、歯科医院での定期的なメンテナンスを受けることが、歯周病予防には欠かせません。歯科医院では、自分では取り除けない歯石や、歯周ポケット内の歯垢を専門的な器具で清掃することができます。
歯科医院で行われるケアの例:
1.スケーリング:歯石を除去し、歯の表面を滑らかにする処置。
2.ルートプレーニング:歯周ポケット内の歯石を取り除き、歯根面を滑らかにする処置。
3.定期検診:歯ぐきの健康状態をチェックし、早期に問題を発見。
これらのプロフェッショナルケアを定期的に受けることで、歯周病を未然に防ぎ、健康な歯ぐきを長く保つことができます。理想的な受診頻度は3~6ヶ月に1回とされていますが、歯科医の指示に従って適切な間隔で受診しましょう。
歯周病を予防するためのカギ

歯周病を予防し、健康な歯ぐきを保つためには、生活習慣の見直しが不可欠です。歯周病は、お口のケアだけでなく、全身の健康とも深く関わっています。健康的な生活習慣を取り入れることで、歯ぐきの状態を改善し、歯周病リスクを軽減することができます。ここでは、生活習慣の改善ポイントを具体的に解説します。
健康な食生活が歯ぐきの状態を改善する理由
栄養バランスの取れた食生活は、歯ぐきの健康に大きな影響を与えます。特に以下の栄養素は歯ぐきの健康維持に効果的です:
1.ビタミンC
ビタミンCは歯ぐきの血管を強化し、炎症を抑える効果があります。不足すると歯ぐきが弱くなり、炎症や出血が起きやすくなります。柑橘類、ブロッコリー、キウイフルーツなどを積極的に摂りましょう。
2.カルシウム
カルシウムは歯を支える歯槽骨を強化するために必要な栄養素です。乳製品、小魚、緑黄色野菜を取り入れることで、歯槽骨の健康を保つことができます。
3.ポリフェノール
緑茶や赤ワインに含まれるポリフェノールは、歯周病菌の増殖を抑える効果があるとされています。特に緑茶には抗菌作用が期待されるカテキンが豊富に含まれています。
◎食事の取り入れ方
・ランチには栄養バランスの取れたメニューを選ぶ(例:野菜が豊富なサラダやスープ)。
・小腹が空いたら、栄養価の高いナッツやヨーグルトをスナックとして活用。
・飲み物は砂糖入りのコーヒーやジュースではなく、緑茶や無糖のハーブティーに切り替える。
適度な運動が全身の免疫力を高める効果
適度な運動は、全身の免疫力を高めるだけでなく、歯周病の予防にもつながります。運動によって血流が促進されると、歯ぐきの血流も改善され、炎症が起きにくい状態を作ることができます。
運動にはストレス軽減効果もあり、これも歯周病予防に寄与します。ストレスが高い状態では、体内で炎症を促進するホルモンが増加し、歯周病リスクが高まることが分かっています。通勤時に一駅分歩く、またはエスカレーターではなく階段を使うことや、週末にはウォーキングやヨガなど、無理なく続けられる運動を日常生活に取り入れると良いでしょう。
身近なリスク因子を減らすためのヒント
歯周病のリスクを軽減するためには、生活習慣に潜むリスク因子を見つけ出し、取り除くことが重要です。
1.禁煙
タバコは歯周病の最大のリスク因子の一つです。喫煙は歯ぐきの血流を阻害し、免疫力を低下させます。禁煙することで歯周病の進行を抑え、治療効果も向上します。
2.睡眠の質を向上させる
睡眠不足は免疫機能を低下させ、歯周病リスクを高めます。十分な睡眠を確保し、体の回復を助けましょう。
3.適切なストレス管理
ストレスは歯周病のリスクを高めるだけでなく、歯ぎしりや食いしばりを引き起こし、歯と歯ぐきに余分な負担をかけます。趣味やリラクゼーションの時間を確保することで、ストレスを軽減しましょう。
リスクを知ることが予防の第一歩

歯周病は「静かなる病気」と呼ばれるように、自覚しにくいまま進行してしまうことが多い病気です。しかし、リスク因子を正しく理解し、適切なケアと生活習慣を取り入れることで予防することが可能です。以下では、これまでの内容を振り返り、歯周病予防における重要なポイントを整理します。
歯周病のリスク因子を知り、対策を始める大切さ
歯周病のリスク因子は、多岐にわたります。お口のケア不足や不適切な生活習慣、全身疾患、ホルモンバランスの変化など、さまざまな要因が歯ぐきの健康に影響を及ぼします。特に以下のような状況に当てはまる方は、早めに対策を始めることが重要です:
・歯ぐきが赤く腫れている、または出血しやすい
・喫煙の習慣がある
・糖尿病や骨粗鬆症などの全身疾患がある
・ストレスや睡眠不足が続いている
こうしたリスク因子を認識し、歯周病の予防に向けて行動を起こすことが、健康を守る第一歩となります。
毎日のケアに加え、定期的な歯科受診の重要性
歯周病予防の基本は、毎日のオーラルケアです。正しいブラッシング方法やデンタルフロス、歯間ブラシの活用は、歯周病菌の増殖を防ぎます。しかし、セルフケアだけでは完全に歯周病を防ぐことはできません。
歯周病は、症状が進行してからでは治療に時間と費用がかかるケースが多いため、定期的な歯科受診が欠かせません。歯科医院では、以下のような専門的なケアを受けることができます:
・スケーリング(歯石除去):歯ブラシでは届かない歯石や歯垢を除去
・歯周ポケットの検査:歯周病の進行具合をチェック
・プロフェッショナルクリーニング:歯と歯ぐきを健康な状態に保つ
理想的な受診頻度は3~6ヶ月に1回ですが、歯科医の指示に従い、自分に合ったケアプランを立てることが大切です。
「気づいた今」が歯周病予防のスタートライン
「忙しいから」「まだ大丈夫だろう」と、歯ぐきの健康を後回しにしていませんか?歯周病は、放置するほど治療が難しくなり、全身の健康に悪影響を及ぼすリスクも高まります。仕事のパフォーマンスを維持するためにも、健康な歯ぐきは欠かせません。
・歯ぐきが腫れている、または出血がある
・朝起きたときに口の中がネバネバする
・歯ぐきが下がり、歯が長く見えるようになった
このような症状を歯科医師や歯科衛生士に相談することで、適切なアドバイスや治療プランを受けることができます。初期段階での対策が、歯周病を防ぎ、健康な歯ぐきを保つためのカギです。
歯周病予防は未来の自分への投資
健康的な歯ぐきは、全身の健康だけでなく、仕事やプライベートでの充実感にもつながります。歯周病予防を日常生活に取り入れることで、より前向きなライフスタイルを実現できます。
仕事のパフォーマンスを維持し、笑顔を輝かせるために、歯周病予防の第一歩を今日から始めましょう。私たち歯科医院は、皆さんが健康な歯ぐきを保つためのサポートを全力で行います。ぜひお気軽にご相談ください!
監修:青山一丁目 麻布歯科
所在地〒:東京都港区赤坂8-5-32 田中駒ビル1F
電話番号☎:03-6434-9877
*監修者
青山一丁目 麻布歯科
ドクター 安達 英一
*出身大学
日本大学歯学部
*経歴
・日本大学歯学部付属歯科病院 勤務
・東京都式根島歯科診療所 勤務
・長崎県澤本歯科医院 勤務
・医療法人社団東杏会丸ビル歯科 勤務
・愛育クリニック麻布歯科ユニット 開設
・愛育幼稚園 校医
・愛育養護学校 校医
・青山一丁目麻布歯科 開設
・区立西麻布保育園 園医
*所属
・日本歯科医師会
・東京都歯科医師会
・東京都港区麻布赤坂歯科医師会
・日本歯周病学会
・日本小児歯科学会
・日本歯科審美学会
・日本口腔インプラント学会
投稿日:2025年1月15日