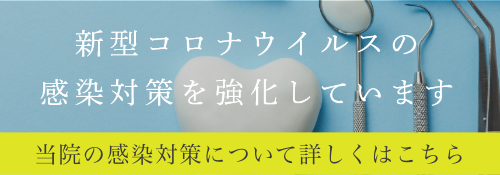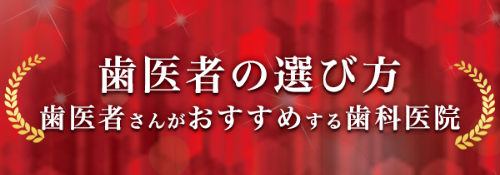歯がしみる原因とは?考えられる4つの要因

① 虫歯による影響—初期段階での発見がカギ
虫歯の初期段階では、自覚症状がほとんどありません。しかし、進行すると冷たいものや甘いものがしみるようになり、症状が悪化するにつれてズキズキとした痛みを伴うことがあります。
- 初期の虫歯(C1):歯の表面のエナメル質がわずかに溶け始める段階で、しみることはほとんどありませんが、歯の表面が白く濁って見えることがあります。
- 中程度の虫歯(C2):象牙質に達すると、冷たいものや甘いものがしみるようになります。痛みはまだ軽度ですが、放置すると進行しやすくなります。
- 重度の虫歯(C3):虫歯が神経に近づくと、温かいものもしみるようになり、ズキズキとした痛みが強くなるのが特徴です。
虫歯の進行を防ぐためには、定期検診を受け、初期段階で発見し治療を行うことが重要です。
② 酸によるエナメル質の損傷—日常の食生活が影響
エナメル質は、歯の表面を守る硬い組織ですが、酸によって溶けやすい特徴があります。特に、酸性度の高い食べ物や飲み物を頻繁に摂取すると、エナメル質が徐々に薄くなり、歯がしみやすくなることがあります。
- 炭酸飲料や柑橘類:コーラやオレンジジュースなどの酸性飲料は、エナメル質を溶かす作用が強いため、頻繁に摂取すると知覚過敏のリスクが高まります。
- ワインや酢の入った食品:酢を多く含むドレッシングやワインも、歯の表面を酸で溶かしやすいため注意が必要です。
- 頻繁な間食:食事の回数が多いと、口の中が常に酸性に傾きやすく、歯の再石灰化(自然修復)が間に合わないため、エナメル質の損傷が進む可能性があります。
酸性食品を摂取した後は、すぐに歯を磨かず、水で口をすすぐことで酸の影響を軽減することが推奨されます。
③ 歯ぎしり・噛みしめによるダメージ
歯ぎしりや強い噛みしめの習慣があると、エナメル質に過度な負担がかかり、摩耗することで知覚過敏を引き起こすことがあります。特に、寝ている間の無意識の歯ぎしりは、長期間にわたって歯をすり減らす原因となります。
- 歯ぎしりによる象牙質の露出:歯の表面が削れることで、エナメル質の下にある象牙質が露出し、冷たいものが直接神経に伝わりやすくなる。
- 噛みしめによる歯の亀裂:強い力で噛みしめることで、歯の表面に微細なヒビ(クラック)が入ることがあり、そこから刺激が神経に伝わることでしみる原因となる。
- ストレスが原因になることも:歯ぎしりや噛みしめは、ストレスが原因で無意識に行っている場合が多いため、リラックスする習慣を身につけることが予防につながる。
歯ぎしりや噛みしめの影響を抑えるために、ナイトガード(マウスピース)の使用や、日常生活でのリラックス習慣を取り入れることが効果的です。
④ 歯ぐきの下がり—加齢や歯周病の影響
加齢や歯周病が原因で歯ぐきが下がると、歯の根元が露出し、しみる症状が現れることがあります。健康な歯ぐきは、歯の根元をしっかり覆っていますが、歯周病が進行すると歯ぐきが退縮し、象牙質がむき出しになることがあります。
- 加齢による歯ぐきの後退:年齢とともに歯ぐきが自然に下がりやすくなり、歯の根元が露出することで知覚過敏の症状が現れることがある。
- 歯周病の影響:歯周病が進行すると、歯ぐきの炎症が悪化し、歯を支える骨が減少することで歯ぐきが下がる。その結果、歯根が露出して冷たいものや歯磨き時の刺激がしみる原因となる。
- 過度なブラッシング:強い力で歯磨きをすると、歯ぐきを傷つけて後退を早めることがあるため、正しいブラッシング方法を実践することが大切。
歯ぐきの下がりが進行すると、歯の根元がむき出しになり、むし歯のリスクも高まるため、適切なケアを行うことが必要です。歯ぐきの健康を維持するためには、歯科医院での定期的な検診と、歯周病予防のケアが不可欠です。
虫歯と知覚過敏の違いとは?セルフチェック方法

① 虫歯の症状—進行とともに痛みが悪化
虫歯は、歯の表面にあるエナメル質が溶け、内部の象牙質や神経に達することで痛みやしみる症状が発生する病気です。虫歯の進行度によって症状が異なり、放置すると痛みが悪化するのが特徴です。
- C1(初期虫歯):エナメル質が溶け始める段階では、自覚症状はほとんどなく、冷たいものがしみる程度の違和感があることがあります。
- C2(象牙質に達する虫歯):象牙質まで進行すると、甘いものや冷たいものがしみる症状が強くなるため、ここで気づく方が多いです。
- C3(神経まで進行):神経に虫歯が達すると、温かいものもしみるようになり、ズキズキとした強い痛みを感じるようになります。
- C4(歯が崩壊):歯の大部分が虫歯によって侵食されると、神経が壊死し、一時的に痛みがなくなることがありますが、最終的に膿が溜まり、強い炎症を引き起こすことがあります。
・ セルフチェックポイント
- 冷たいものだけでなく、甘いものや温かいものもしみる → 虫歯の可能性大
- しみる症状が続く、もしくは痛みに変わる → 虫歯の進行が疑われる
- 歯の一部分に黒い変色がある → 虫歯の初期症状
虫歯が原因のしみる症状は、進行すると痛みが強くなるため、できるだけ早めに治療を受けることが重要です。
② 知覚過敏の症状—一時的な刺激による違和感
知覚過敏は、虫歯がないのに歯がしみる症状を引き起こす状態です。これは、歯のエナメル質が薄くなったり、象牙質が露出したりすることで神経に刺激が伝わりやすくなるために起こります。
知覚過敏の特徴は、一時的にしみるが、痛みが長く続かないことです。例えば、冷たいものを飲んだ瞬間にしみても、すぐに症状が消える場合は、知覚過敏の可能性が高いです。
- 象牙質の露出が原因:エナメル質が削れると、象牙細管(歯の内部にある小さな管)を通じて神経が刺激を受けやすくなるため、しみやすくなります。
- ブラッシングの影響:強い力で歯を磨きすぎると、歯ぐきが下がり、知覚過敏を引き起こすことがあるため、注意が必要です。
- ホワイトニングの影響:ホワイトニング後に一時的に知覚過敏の症状が出ることがあり、時間とともに回復するケースが多いです。
・ セルフチェックポイント
- 冷たいものを口に含むと一瞬しみるが、すぐに治る → 知覚過敏の可能性大
- 特定の食べ物や飲み物でしみるが、時間が経つと気にならない → 知覚過敏の症状
- 歯ブラシを当てたときにしみる → 知覚過敏の特徴的な症状
知覚過敏は、適切なセルフケアを行うことで改善できることが多いため、歯磨きの方法や使用するケア用品を見直すことが重要です。
③ 虫歯と知覚過敏を見分けるための簡単チェックリスト
自分の症状が虫歯なのか、知覚過敏なのかを判断するために、以下のチェックリストを活用してみてください。
・ 虫歯の特徴
- 甘いものがしみる
- しみる症状が長く続く
- 歯の表面に黒い点や穴がある
- 噛むと痛みを感じる
- しみる場所が特定できる(1本の歯に集中)
・ 知覚過敏の特徴
- 冷たいものを食べると一瞬しみるが、すぐに治まる
- 強く歯磨きをするとしみる
- 甘いものや温かいものではしみない
- 食事のたびに症状が変わる
このチェックリストで虫歯の可能性が高いと感じた場合は、早めに歯科医院で診察を受けることをおすすめします。
虫歯が原因の「しみる」を放置するとどうなる?
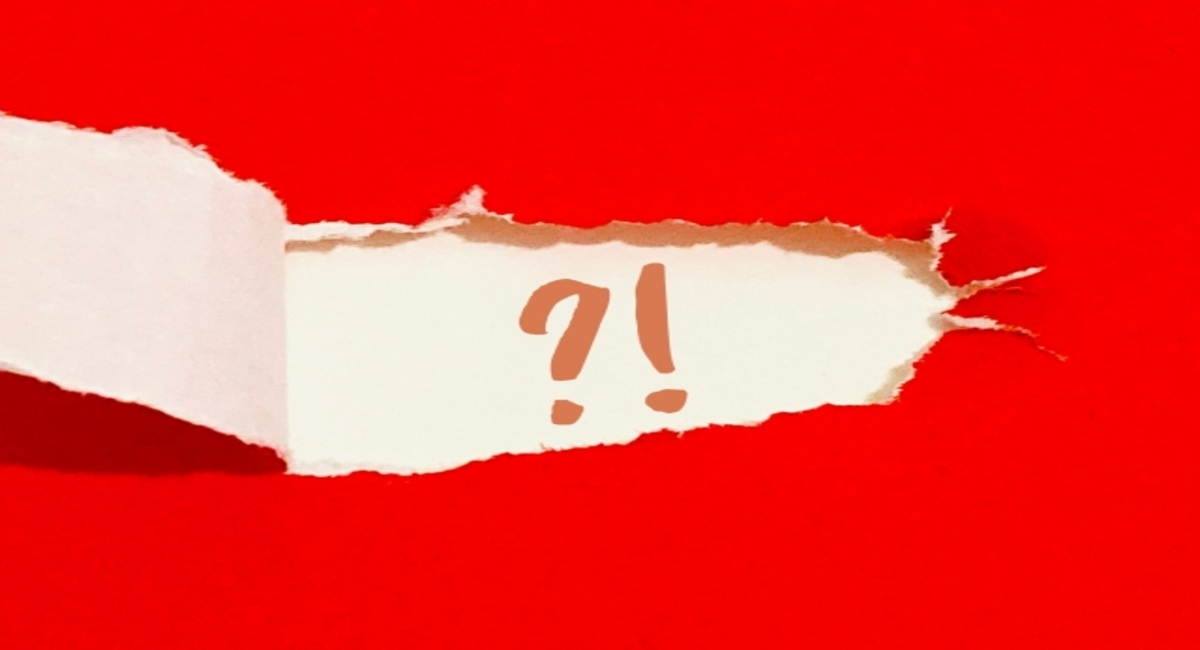
① 初期段階なら痛みがなくても要注意!進行すると神経が侵される
虫歯の初期段階では、しみる程度の軽い症状しか感じないことが多いため、見逃しやすいですが、この段階で適切な対応をすることで進行を防ぐことができます。
- C1(初期の虫歯):歯の表面のエナメル質に穴が開き始める段階。痛みはほとんどなく、冷たいものや甘いものを食べたときに軽くしみる程度ですが、すぐに消えるため見過ごされることが多い。
- C2(中程度の虫歯):象牙質に達すると、しみる症状が強くなり、甘いものや冷たいものが刺激になる。この段階では痛みが出ることもあるが、まだ神経まで達していないため、詰め物で対応できるケースが多い。
- C3(神経に達する虫歯):歯の内部にある歯髄(神経)に虫歯が到達すると、ズキズキとした痛みを感じるようになり、熱いものでもしみる症状が現れる。この段階では、神経を取り除く「根管治療」が必要になることがほとんど。
・ 放置するとどうなる?
- 初期のしみる症状を放置すると、やがて強い痛みに変わる
- 冷たいものだけでなく、甘いものや温かいものもしみるようになる
- 進行すればするほど治療の選択肢が限られ、治療期間も長くなる
初期段階の虫歯であれば、簡単な詰め物(レジン充填)で治療が可能ですが、進行すると削る量が増え、最終的には神経を抜く治療が必要になります。
② 歯の内部まで虫歯が進行すると治療が大がかりになることも
虫歯が進行すると、歯の内部(歯髄)に細菌が感染し、激しい痛みを伴うことがあります。この場合、通常の虫歯治療では対応できず、根管治療(歯の神経の治療)が必要になります。
根管治療が必要なケース
虫歯が神経まで達すると、ズキズキとした強い痛みが続き、最終的には神経が壊死してしまいます。神経が壊死すると、一時的に痛みが消えることもありますが、根の先に膿がたまり、歯ぐきが腫れる原因になります。
根管治療の流れ
- 感染した神経を取り除く
- 歯の内部を清掃して消毒する
- 薬を詰めて封鎖し、炎症を抑える
- 最終的に被せ物(クラウン)で補う
根管治療は数回の通院が必要になり、歯の強度が低下するため、被せ物(クラウン)を使用することが一般的です。
・ 根管治療を放置すると…
- 細菌が顎の骨まで広がり、膿がたまる「歯根嚢胞(しこんのうほう)」ができる
- 骨を溶かす「歯根破折」が発生する
- 最終的に抜歯が必要になる可能性が高まる
・ 放置するとどうなる?
- 根管治療が必要になり、通院回数が増える
- 歯の強度が低下し、最終的に被せ物が必要になる
- 感染が広がると抜歯が必要になる可能性が高くなる
歯の内部まで虫歯が進行すると、治療が大がかりになるだけでなく、歯を失うリスクも高まるため、早めの治療が重要です。
③ 歯を残すためには早期発見・早期治療が鍵!
虫歯が原因のしみる症状を放置すると、最終的には歯を失うリスクが高まります。歯を残すためには、早期発見・早期治療が最も重要です。
定期検診を受ける
- 虫歯は初期段階では自覚症状が少ないため、定期的な歯科検診を受けることで、早期に発見しやすくなります。
- 特に、半年に一度の定期検診を受けることで、虫歯の進行を防ぐことができます。
フッ素塗布で予防する
- 虫歯の予防には、フッ素塗布が有効です。
- フッ素には歯の再石灰化を促進し、エナメル質を強化する働きがあるため、虫歯になりにくい歯を作ることができます。
- 市販のフッ素入り歯磨き粉を使用することも効果的ですが、歯科医院で行うフッ素塗布は濃度が高く、より強力な予防効果が期待できます。
適切な歯磨きを心がける
- 虫歯予防には、正しい歯磨きが不可欠です。
- 特に、フッ素配合の歯磨き粉を使用し、歯と歯の間や奥歯までしっかり磨くことが大切です。
- また、歯磨きだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、より効果的に虫歯を予防することができます。
・ 歯を残すために今すぐできること
- しみる症状が続く場合は、早めに歯科医院で診断を受ける
- 定期検診を受け、虫歯を早期発見する
- フッ素塗布や適切な歯磨きで、虫歯の進行を防ぐ
知覚過敏はなぜ起こる?歯のエナメル質が関係している

① エナメル質がすり減ると歯がしみやすくなる
歯の表面を覆っているエナメル質は、体の中で最も硬い組織ですが、酸や摩擦、歯ぎしりなどによって徐々にすり減ることがあります。これにより、エナメル質の下にある象牙質が露出し、外部からの刺激が直接神経に伝わりやすくなります。
エナメル質の役割とは?
エナメル質は、歯を外部の刺激から守るためのバリアのような役割を持っています。通常、冷たいものや熱いものを口に含んでも神経には影響しませんが、エナメル質が薄くなると、象牙細管(象牙質にある細い管)を通じて刺激が歯の神経に直接伝わるようになるため、知覚過敏の症状が現れます。
エナメル質がすり減る原因
- 強いブラッシング(ゴシゴシ磨きすぎるとエナメル質が削れる)
- 酸性食品の摂取(炭酸飲料・柑橘類・酢などの摂取頻度が多いとエナメル質が溶けやすくなる)
- 歯ぎしり・食いしばり(歯がすり減り、象牙質が露出する)
- 加齢による摩耗(長年の使用でエナメル質が自然に薄くなることもある)
・ エナメル質の摩耗を防ぐには?
- 強い力で歯磨きをしない(やさしくブラッシング)
- 酸性食品を摂取した後は、すぐに歯を磨かず水で口をすすぐ
- フッ素配合の歯磨き粉を使用して、エナメル質の再石灰化を促す
② 歯ぎしり・強いブラッシングが知覚過敏を引き起こす
知覚過敏の原因の一つに歯ぎしりや強いブラッシングがあります。無意識に歯ぎしりをしている方や、力強く歯磨きをする習慣がある方は、エナメル質がすり減りやすいため、知覚過敏のリスクが高まります。
歯ぎしりによる影響
寝ている間に歯ぎしりをしていると、エナメル質が摩耗し、象牙質が露出することで知覚過敏が起こります。さらに、歯ぎしりは歯や歯ぐきに過度な負担をかけ、歯の亀裂や欠け、歯周病の悪化などの原因にもなります。
強いブラッシングの影響
歯をゴシゴシと強く磨くことで、歯の表面が削られ、エナメル質が薄くなることがあります。また、歯ぐきを傷つけることで、歯ぐきの退縮を引き起こし、象牙質が露出して知覚過敏を悪化させる可能性があります。
・ 歯ぎしりや強いブラッシングを防ぐには?
- 寝ている間の歯ぎしり対策として、ナイトガード(マウスピース)を使用する
- 歯ブラシは柔らかめを選び、優しく小刻みにブラッシングする
- 知覚過敏用の歯磨き粉を使用し、象牙質を保護する
③ ホワイトニング後に歯がしみるのはなぜ?
ホワイトニングを受けた後に、一時的に歯がしみると感じる方もいます。これは、ホワイトニング剤の影響でエナメル質の表面が一時的に脱水状態になり、象牙質が刺激を受けやすくなるためです。
ホワイトニング後の知覚過敏の特徴
ホワイトニング直後は、冷たいものや熱いものを口に含んだ際に、一時的にしみる感覚が現れることがあります。しかし、多くの場合は数日〜1週間ほどで症状が軽減し、元の状態に戻ります。
ホワイトニングによる知覚過敏を防ぐ方法
- ホワイトニング直後は、極端に冷たい・熱いものを避ける
- 知覚過敏用の歯磨き粉を使用し、歯を保護する
- 歯科医院で適切なホワイトニング方法を相談する
・ ホワイトニング後の知覚過敏は一時的なものであることが多いため、過度に心配する必要はありません。
しかし、症状が長期間続く場合は、ホワイトニングの影響以外の要因(歯ぎしり・歯周病など)が関与している可能性があるため、歯科医院で相談することをおすすめします。
歯ぐきが下がると歯がしみる?歯周病との関係性

① 加齢による歯ぐきの後退が知覚過敏を悪化させる
歯ぐきの下がりは、年齢とともに自然に起こる現象でもあります。特に50代以降になると、歯ぐきが徐々に後退し、歯の根元が露出しやすくなるため、しみる症状が現れやすくなります。
歯ぐきが下がると何が起こる?
健康な歯ぐきは、歯の根元を覆い、外部からの刺激から歯を守っています。しかし、歯ぐきが後退すると、エナメル質に覆われていない象牙質が露出し、冷たいものや歯磨きの刺激が直接神経に伝わるようになります。
加齢とともに歯ぐきが痩せる理由
- 歯周組織の老化(歯ぐきの弾力が低下し、後退しやすくなる)
- 唾液の減少(口腔内が乾燥すると、歯ぐきがダメージを受けやすくなる)
- 長年のブラッシングの影響(強い力で磨くことで歯ぐきを傷つけ、徐々に下がってしまう)
・ 加齢による歯ぐきの下がりを防ぐには?
- 歯ぐきを傷つけないように、やさしくブラッシングする
- 定期的に歯科医院で歯ぐきの状態をチェックする
- 歯ぐきの血行を促進するマッサージを取り入れる
② 歯周病が進行すると歯根が露出し、しみやすくなる
歯ぐきの下がりの最も大きな原因の一つが歯周病です。歯周病が進行すると、歯を支えている骨(歯槽骨)が溶け、歯ぐきが下がることで知覚過敏の症状が現れることがあります。
歯周病の進行と歯ぐきの退縮
- 軽度の歯周炎(歯ぐきの炎症):歯ぐきが赤く腫れ、ブラッシング時に出血することがあるが、まだ歯ぐきの後退は少ない。
- 中等度の歯周病(歯周ポケットの深まり):歯ぐきの腫れが慢性化し、歯周ポケット(歯と歯ぐきの間の隙間)が深くなる。歯ぐきが後退し、歯の根元が露出し始める。
- 重度の歯周病(歯を支える骨が溶ける):歯ぐきが大きく下がり、歯のぐらつきが起こる。冷たいものや甘いものがしみるだけでなく、噛むと痛みを感じることもある。
・ 歯周病による歯ぐきの下がりを防ぐには?
- 歯科医院での定期的なクリーニングを受け、歯周病を予防する
- 正しいブラッシング方法を実践し、歯ぐきに優しいケアを行う
- 歯ぐきの健康を維持するために、ビタミンCやカルシウムを含む食品を摂取する
③ 正しい歯磨きとケアで歯ぐきを守る方法
歯ぐきを健康に保ち、知覚過敏を防ぐためには、日々の正しい口腔ケアが不可欠です。歯ぐきに負担をかけず、優しくケアすることで、歯ぐきの退縮を防ぐことができます。
適切な歯磨きの方法
- 歯ブラシは「やわらかめ」を選び、力を入れすぎずに磨く
- 歯ぐきをマッサージするように、円を描くようにブラッシングする
- デンタルフロスや歯間ブラシを活用し、歯と歯の間の汚れをしっかり除去する
歯ぐきのマッサージを取り入れる
歯ぐきの血流を促進し、健康な状態を維持するためには、指や柔らかい歯ブラシで歯ぐきを軽くマッサージすることが効果的です。
知覚過敏用の歯磨き粉を使用する
知覚過敏の症状がある場合は、知覚過敏専用の歯磨き粉を使用すると、歯の神経を保護し、症状を緩和することができます。
・ 歯ぐきを守るためにできること
- 優しいブラッシングを心がけ、歯ぐきを傷つけないようにする
- 定期的に歯科医院で歯周病のチェックを受ける
- 知覚過敏用の歯磨き粉を活用し、歯の根元を保護する
自宅でできる「しみる歯」のセルフケア方法

① 知覚過敏用の歯磨き粉で歯をコーティング
知覚過敏の症状がある場合、知覚過敏専用の歯磨き粉を使用することで、歯の神経を保護し、刺激を軽減することができます。
知覚過敏用歯磨き粉の仕組み
知覚過敏用の歯磨き粉には、象牙細管(神経に通じる細い管)を封鎖する成分や、神経の興奮を抑える成分が含まれているため、継続的に使用することで症状が和らぐことが期待できます。
主な成分と効果
- 硝酸カリウム(神経の過敏反応を抑制)
- フッ素(歯の再石灰化を促し、エナメル質を強化)
- ヒドロキシアパタイト(象牙細管を埋めて刺激を遮断)
知覚過敏用歯磨き粉の使い方
- 通常の歯磨きと同じように、1日2回使用する。
- 強く磨かず、優しく歯の表面をコーティングするようにブラッシングする。
- 磨いた後、口をすすぎすぎないことで、歯磨き粉の成分が長く歯に留まり、効果を発揮しやすくなる。
歯磨き粉を活用することで、継続的に症状を和らげることができるため、知覚過敏を感じたらすぐに試してみましょう。
② フッ素配合のケア用品で歯を強くする
フッ素は、歯のエナメル質を強化し、虫歯や知覚過敏の予防に役立つ成分です。特に、エナメル質が摩耗している場合や、酸の影響で歯が弱くなっている場合には、フッ素を活用することで歯の耐久性を高めることができます。
フッ素の働き
- 歯の再石灰化を促進し、エナメル質を修復する
- 酸による歯の溶解(脱灰)を防ぎ、強い歯を作る
- 知覚過敏の症状を軽減し、しみる原因を抑える
フッ素を取り入れる方法
- フッ素配合の歯磨き粉を使用する(1450ppmの濃度が効果的)
- フッ素洗口液(マウスウォッシュ)を併用する
- 歯科医院で高濃度フッ素塗布を受ける
フッ素配合のケア用品を日常的に取り入れることで、歯の表面を強化し、しみる症状を軽減することができます。
③ 刺激の少ない食べ物・飲み物を選ぶことが重要
食生活も、歯の健康や知覚過敏の予防に大きな影響を与える要素です。特に、酸性度の高い食べ物や炭酸飲料は、歯のエナメル質を溶かしやすく、知覚過敏を悪化させる原因になるため、注意が必要です。
避けるべき食品・飲み物
- 炭酸飲料(コーラ、エナジードリンクなど)
- 柑橘類(レモン・グレープフルーツなど)
- 酢を含む食品(ピクルス・ドレッシングなど)
- 砂糖を多く含む食品(チョコレート・飴など)
おすすめの食品・飲み物
- 乳製品(牛乳・チーズ・ヨーグルト):カルシウムが豊富で歯の再石灰化を助ける
- 緑黄色野菜(ほうれん草・にんじん・ブロッコリー):ビタミンA・Cが豊富で、歯ぐきの健康を維持
- ナッツ類(アーモンド・クルミなど):歯を強くするリンやマグネシウムが含まれる
また、食後はすぐに歯を磨かず、水で口をすすぐことで酸の影響を軽減し、エナメル質を保護することができます。食生活を見直すことで、知覚過敏の症状を軽減し、歯の健康を守ることができます。
歯がしみるときに避けるべきNG習慣

① 歯ぎしり・食いしばりがエナメル質を傷つける
寝ている間の歯ぎしりや、日中の無意識な食いしばりは、歯の表面に大きな負担をかけ、エナメル質をすり減らす原因になります。歯ぎしりを続けていると、歯が摩耗し、象牙質が露出してしまうため、冷たいものや歯磨きの際にしみるようになります。
歯ぎしりが及ぼす影響
- エナメル質が削れ、知覚過敏の症状が悪化する
- 歯の表面に小さなヒビ(マイクロクラック)が入り、刺激が神経に伝わりやすくなる
- 強い力がかかることで、歯ぐきが下がり、歯の根元が露出しやすくなる
食いしばりの習慣をチェックする方法
- 朝起きたときに顎が疲れている、痛みを感じる
- 日中、仕事や運転中に無意識に歯を食いしばっていることがある
- 歯の先端がすり減っている、削れたように見える
歯ぎしり・食いしばりの対策
- 寝るときにナイトガード(マウスピース)を装着する
- 日中、意識して顎の力を抜く(リラックスする習慣を持つ)
- 歯科医院で噛み合わせのチェックを受け、必要に応じて調整する
歯ぎしりや食いしばりは、歯の摩耗や知覚過敏を悪化させるため、意識的に対策を取ることが重要です。
② 片側だけで噛む習慣が歯の負担を増やす
食事のときに、片側の歯ばかり使って噛んでいると、歯に偏った負担がかかり、しみる症状の原因になることがあります。これは、使っていない側の歯ぐきが徐々に下がり、象牙質が露出しやすくなるためです。
片側噛みが引き起こす影響
- 使わない側の歯ぐきが退縮し、歯根が露出する
- 片側の歯に負担が集中し、エナメル質がすり減りやすくなる
- 顎の筋肉のバランスが崩れ、顎関節症の原因になることもある
片側噛みを防ぐための習慣
- 食事の際に、意識的に両側の歯を使って噛む
- 噛みにくい側にむし歯や詰め物の違和感がある場合は、早めに歯科医院で調整する
- 硬い食べ物ばかり食べるのを避け、バランスの良い食事を心がける
片側噛みの習慣を見直すことで、歯への負担を分散し、知覚過敏のリスクを軽減できます。
③ 口呼吸が歯の乾燥を招き、しみる原因になる
口呼吸の習慣があると、口の中が乾燥し、歯のエナメル質が弱くなることで、知覚過敏の症状が現れやすくなります。これは、唾液が不足することで歯の再石灰化が十分に行われず、歯が酸の影響を受けやすくなるためです。
口呼吸が歯に与える影響
- 唾液の分泌が減少し、エナメル質の保護が弱まる
- 口腔内が乾燥し、歯ぐきが炎症を起こしやすくなる
- 口臭や歯周病のリスクが高まる
口呼吸を防ぐための方法
- 鼻呼吸を意識し、日中も口を閉じる習慣をつける
- 寝るときにマスクを着用する、口テープを使って鼻呼吸を促す
- 歯科医院で口呼吸の原因(鼻づまり、歯並びの問題など)を相談する
口呼吸の習慣を改善することで、口の中の乾燥を防ぎ、歯を守ることができます。
歯科医院でできる「しみる歯」の治療法とは?

① 知覚過敏用のコーティング剤で刺激をブロック
知覚過敏の症状がある場合、歯の表面を保護するコーティング剤を塗布することで、象牙質への刺激をブロックし、しみる症状を軽減することができます。
コーティング剤の種類と特徴
- フッ化物(フッ素コーティング):歯の再石灰化を促進し、エナメル質を強化する
- グルタルアルデヒド:象牙質のタンパク質を変性させ、象牙細管を閉じることで刺激を遮断する
- レジン(歯科用シーラント):歯の表面を薄い樹脂で覆い、刺激を直接受けないようにする
治療の流れ
- 歯の表面をクリーニングし、汚れを除去する
- 知覚過敏の部分にコーティング剤を塗布する
- しばらく放置して定着させた後、乾燥させる
コーティング剤は即効性があり、塗布直後からしみる症状が軽減されることが多いですが、定期的なメンテナンスが必要になる場合もあります。
② 虫歯が原因なら適切な治療を受けることが大切
歯がしみる原因が虫歯である場合、早期に適切な治療を受けることで、進行を防ぐことができます。 虫歯の進行度によって治療法が異なりますが、症状が軽いうちに治療を行えば、歯への負担を最小限に抑えることができます。
虫歯の進行度別の治療法
- C1(エナメル質の虫歯):フッ素塗布やレジン(樹脂)を詰めることで対応可能
- C2(象牙質に達した虫歯):詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)で保護
- C3(神経に達した虫歯):神経を除去する根管治療(歯の神経の処置)が必要
- C4(重度の虫歯):歯を保存できない場合は抜歯し、インプラントやブリッジを検討
虫歯治療後のケアが重要
- 虫歯治療を受けた後も、再発を防ぐために正しい歯磨き習慣や定期検診を継続することが大切
- 詰め物や被せ物をした歯でも、適切なケアを怠ると二次虫歯(再発)が起こる可能性がある
しみる症状が続く場合は、虫歯が進行している可能性があるため、早めに歯科医院で診察を受けることが重要です。
③ 歯ぐきが下がっている場合の再生治療とは?
歯ぐきが下がることで歯の根元が露出し、知覚過敏を引き起こしている場合、歯ぐきを保護するための再生治療が有効なケースがあります。
歯ぐきの再生治療(結合組織移植術)
- 自分の口の中から健康な歯ぐきを採取し、後退した部分に移植する
- 歯ぐきの厚みを増やすことで、知覚過敏を軽減し、歯根を保護する
歯周病が原因の場合の治療
- スケーリング・ルートプレーニング(歯石除去と歯根の清掃)
- 歯周ポケットの深さを測定し、進行度に応じた治療を行う
レーザー治療による知覚過敏の緩和
- レーザーを照射し、歯の神経を鈍らせることでしみる症状を抑える
- 短時間で施術が完了し、痛みが少ないのが特徴
歯ぐきが下がることでしみる症状がある場合は、歯科医院での専門的な治療が必要になることがあります。
PMTC(プロフェッショナルクリーニング)で歯の健康を守る!

① 歯の表面を傷つけずに汚れを徹底除去
日常の歯磨きでは、どれだけ丁寧に磨いていても、歯と歯の間や歯ぐきの隙間に汚れが残ってしまうことがあります。その結果、歯垢や歯石が蓄積し、虫歯や歯周病のリスクが高まるとともに、知覚過敏の原因にもなります。
PMTCでは、歯科医師や歯科衛生士が専用の器具を使って歯を徹底的に清掃し、歯垢や歯石を取り除くことで、歯の健康を保ちます。
PMTCの施術内容
- 専用の器具で歯垢や歯石を除去するスケーリング
- 研磨剤を使用し、歯の表面を滑らかにするポリッシング
- フッ素を塗布し、エナメル質を強化する
歯科医院でのPMTCを定期的に受けることで、歯の表面がなめらかになり、汚れが付着しにくくなるため、知覚過敏の症状を予防しやすくなります。
② 歯ぐきのマッサージで血行促進し、歯周病予防にも効果的
PMTCでは、歯の表面だけでなく、歯ぐきのケアも重要視されます。歯ぐきが健康であれば、歯根が露出するリスクを減らし、知覚過敏の症状が出にくくなるため、歯ぐきのマッサージや血行促進も大切なポイントとなります。
歯ぐきマッサージの効果
- 歯ぐきの血行を促進し、健康な状態を維持する
- 歯周病の進行を抑え、歯ぐきの退縮を防ぐ
- 歯ぐきの腫れや炎症を軽減し、しみる症状を抑える
PMTCで行われる歯ぐきのケア
- 専用の機器で歯ぐきの表面をやさしく刺激し、血流を良くする
- 歯周ポケットの奥にある歯垢や細菌を取り除く
- 歯ぐきを引き締め、知覚過敏の進行を防ぐ
PMTCの施術を定期的に受けることで、歯ぐきの健康を保ち、知覚過敏や歯がしみる原因を予防することができます。
③ 定期的なクリーニングで歯のしみを予防する
歯がしみる症状を防ぐためには、定期的にPMTCを受け、口腔内の健康を維持することが重要です。PMTCを受けることで、歯垢や歯石が溜まりにくくなり、虫歯や知覚過敏のリスクを大幅に軽減することができます。
PMTCを受ける頻度の目安
- 健康な歯を維持するためには、3〜6ヶ月に1回の施術が推奨される
- 知覚過敏の症状がある場合は、歯科医師と相談しながら頻度を決める
- 歯周病が進行している場合は、より短い間隔での施術が必要になることもある
PMTCが知覚過敏や虫歯予防に効果的な理由
- 歯の表面を滑らかにすることで、象牙質の露出を防ぐ
- フッ素コーティングにより、エナメル質を強化し、刺激を軽減する
- 歯周病の予防につながり、歯ぐきの退縮を抑えることで、知覚過敏のリスクを低減する
PMTCを継続して受けることで、知覚過敏や虫歯の進行を防ぎ、しみる症状を根本から改善することが可能です。
歯がしみる症状が続くなら、早めに歯科医院へ!
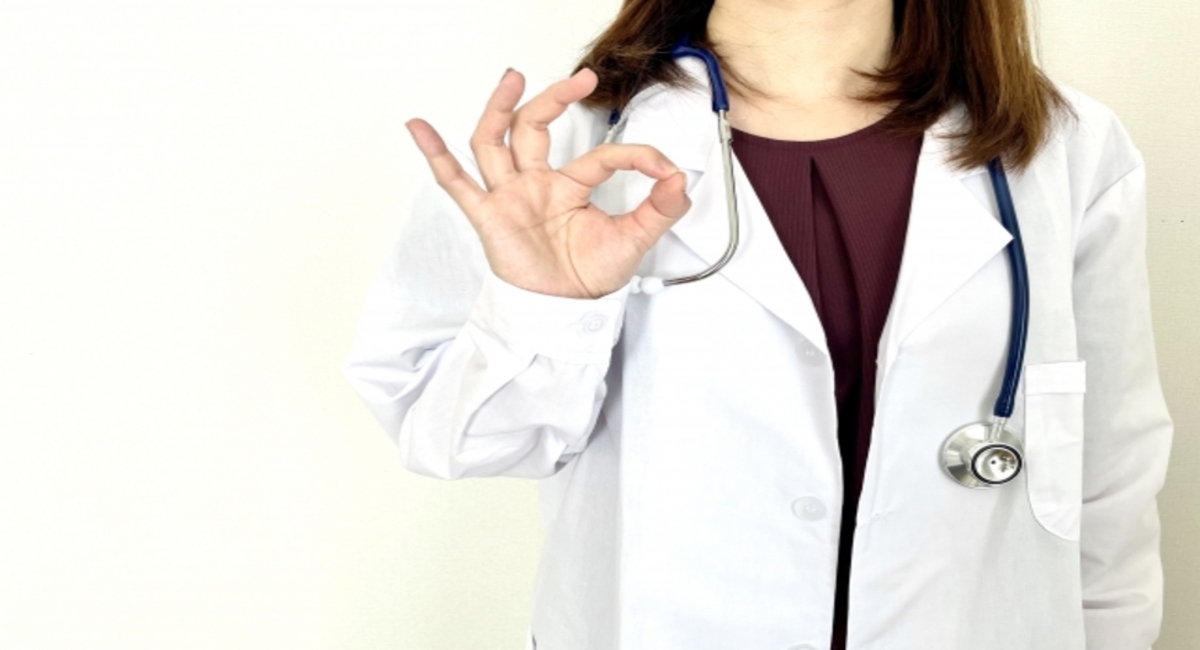
① 自己判断せず、専門医に相談することが重要
歯がしみる症状が出たときに「様子を見よう」と放置してしまう方も少なくありません。しかし、しみる原因が虫歯や歯周病の場合、放置することで症状が進行し、より大掛かりな治療が必要になることがあります。
歯がしみる原因を見極めるのは難しい
- 知覚過敏、虫歯、歯周病、歯ぎしり、酸蝕症などの原因が考えられるが、自分で正確に診断するのは難しい
- 専門的な診察を受けることで、適切な治療法が選択できる
放置することで症状が悪化する可能性がある
- 初期の知覚過敏であれば、セルフケアで症状を軽減できることもあるが、歯の神経に問題がある場合は強い痛みや炎症を引き起こす可能性がある
適切なタイミングで受診することが大切
- 歯がしみる症状が一時的であれば問題ない場合もあるが、1週間以上続く場合や、食事のたびにしみる感覚がある場合は、早めに受診することが推奨される
② 知覚過敏も放置すると悪化する可能性がある
知覚過敏は、初期段階では軽い違和感だけですが、適切なケアをせずに放置すると症状が悪化する可能性があります。
知覚過敏の進行によるリスク
- 歯の象牙質がさらに露出し、より強い刺激を感じるようになる
- 歯ぐきが退縮し、歯根が露出することでしみる範囲が広がる
- 知覚過敏の症状が続くことで、食事や歯磨きの際にストレスを感じやすくなる
歯科医院での治療が必要になるケース
- 知覚過敏の症状が1ヶ月以上続く
- フッ素塗布や知覚過敏用歯磨き粉を使用しても改善が見られない
- 噛むと痛みを感じる場合(歯のひび割れが原因の可能性)
知覚過敏の治療としては、フッ素塗布、コーティング剤の塗布、レーザー治療などが効果的ですが、自己判断で放置せず、専門家に相談することでより適切なケアを受けることができます。
③ 定期検診を受けて、健康な歯を維持しよう
歯がしみる症状を未然に防ぎ、口腔内の健康を維持するためには、定期的に歯科検診を受けることが大切です。
定期検診を受けるメリット
- 虫歯や歯周病の早期発見・早期治療が可能になる
- 歯のクリーニングを受けることで、歯石やプラークを除去できる
- 知覚過敏の進行を防ぐためのケアを受けることができる
歯科検診の推奨頻度
- 健康な歯を維持するためには、3〜6ヶ月に1回の定期検診が推奨される
- 知覚過敏の症状がある場合は、歯科医師と相談しながら頻度を決める
- 歯周病が進行している場合は、より短い間隔での検診が必要になることもある
定期検診では、虫歯や知覚過敏の進行状況をチェックし、適切な予防策を講じることができます。また、歯のクリーニングを受けることで、汚れが付きにくくなり、歯の健康を長く維持することができます。
監修:青山一丁目 麻布歯科
所在地〒:東京都港区赤坂8-5-32 田中駒ビル1F
電話番号☎:03-6434-9877
*監修者
青山一丁目 麻布歯科
ドクター 安達 英一
*出身大学
日本大学歯学部
*経歴
・日本大学歯学部付属歯科病院 勤務
・東京都式根島歯科診療所 勤務
・長崎県澤本歯科医院 勤務
・医療法人社団東杏会丸ビル歯科 勤務
・愛育クリニック麻布歯科ユニット 開設
・愛育幼稚園 校医
・愛育養護学校 校医
・青山一丁目麻布歯科 開設
・区立西麻布保育園 園医
*所属
・日本歯科医師会
・東京都歯科医師会
・東京都港区麻布赤坂歯科医師会
・日本歯周病学会
・日本小児歯科学会
・日本歯科審美学会
・日本口腔インプラント学会
投稿日:2025年3月14日