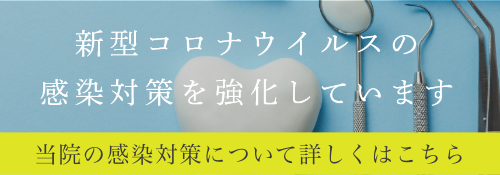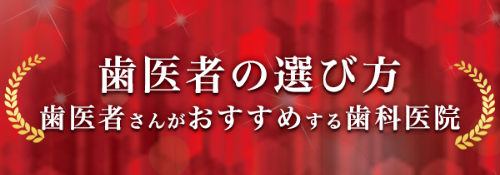はじめに:なぜ歯の痛みは放置してはいけないのか?

痛みは体のSOSサイン!放置するとどうなる?
歯の痛みは、体が発する重要なSOSサインです。「少し痛むけど、そのうち治るかも…」と放置してしまうと、思わぬトラブルに発展することがあります。歯の痛みは多くの場合、虫歯や歯周病、神経の炎症など、何らかの病変が進行していることを示しています。
放置することで起こる代表的なトラブルは以下のとおりです。
・虫歯の悪化
初期段階では軽い痛みやしみる程度だった虫歯が、放置することで神経に達し、激痛を伴う状態へと進行します。やがて神経が壊死すると一時的に痛みが消えることもありますが、感染が広がり、さらに大きな治療が必要になります。
・歯周病の進行
歯ぐきが腫れたり出血したりする段階であれば、適切な治療で進行を防げます。しかし、放置すると歯を支える骨が溶けてしまい、最悪の場合、歯が抜けてしまうこともあります。
・顎や全身への影響
放置した炎症が顎の骨や他の部位へと広がり、顔が腫れたり発熱を伴ったりすることもあります。さらに、細菌が血液を介して全身に広がる「敗血症」などの重篤な症状を引き起こす可能性もあります。
痛みが一時的に消えても安心できない理由
歯が痛んでいたのに、ある日突然痛みが消えた…この場合、むしろ注意が必要です。痛みが消えたのは、単に症状が落ち着いただけであり、病気が治癒したわけではないことがほとんどだからです。
痛みが消えるケースとして、以下のような原因が考えられます。
・神経が壊死してしまった場合
虫歯が進行して神経に到達すると、強い痛みを感じます。しかし、そのまま放置すると神経が死んでしまい、一時的に痛みを感じなくなります。ところが、神経のない歯は感染の温床となり、気づかないうちに炎症が顎の骨に広がることがあります。
・歯周病が慢性化した場合
初期の歯周病では歯ぐきが腫れたり痛みを感じたりすることがありますが、慢性化すると痛みが減少することがあります。痛みがないからといって放置すると、歯を支える骨がどんどん溶け、最終的に歯が抜けてしまうこともあります。
・噛み合わせの変化による一時的な軽減
歯ぎしりや食いしばり、詰め物の不具合などが原因で痛みが出ていた場合、一時的に噛み合わせが変わることで痛みが軽減することがあります。しかし、根本的な原因が解決されない限り、再発する可能性が高いです。
早期治療のメリットと、治療が遅れるデメリット
歯の痛みを感じたら、できるだけ早めに治療を受けることが重要です。早期に対応することで、治療の負担が軽減され、より健康な状態を維持することができます。
【早期治療のメリット】
・治療が簡単で痛みが少ない
初期の虫歯や歯周病であれば、比較的短期間かつ簡単な治療で改善できます。痛みを感じる前に治療を受けることで、神経を取るような大がかりな治療を避けられる可能性が高くなります。
・治療費が抑えられる
例えば、初期の虫歯であれば小さな詰め物(コンポジットレジン)で済みますが、進行すると神経の治療(根管治療)が必要になり、費用も大幅に増えます。また、最悪の場合、抜歯が必要となり、インプラントやブリッジなどの費用がかかることになります。
・歯を長く健康に保てる
早期に治療を受けることで、歯を削る量を最小限に抑えたり、歯ぐきを健康な状態に保つことができます。これは、将来的に自分の歯を残すためにも非常に重要です。
【治療が遅れるデメリット】
・痛みが悪化し、日常生活に支障をきたす
軽い違和感だったものが、ある日突然強い痛みに変わることがあります。特に夜間や仕事中に激痛が走ると、食事や睡眠にも影響を及ぼします。
・治療期間が長くなる
初期段階の治療であれば1回の通院で済むこともありますが、重症化すると何度も通院しなければならなくなります。根管治療や歯周病の外科治療が必要になると、数カ月単位での治療が必要になることもあります。
・歯を失うリスクが高まる
進行した虫歯や歯周病は、抜歯が必要になるケースが増えます。一度失った歯は自然に再生することはないため、インプラントや義歯などの補綴治療が必要になり、負担が大きくなります。
歯の痛みを感じたら、自己判断で様子を見るのではなく、できるだけ早めに歯科医院を受診することが最善の選択肢です。治療を先延ばしにせず、早めの行動を心がけましょう。
歯周病による痛み:歯ぐきの腫れや出血を伴うケース
虫歯だけでなく、歯周病も歯が痛くなる原因のひとつです。歯周病は、歯ぐきの炎症によって痛みを引き起こし、進行すると歯を支える骨が溶けてしまいます。
・歯肉炎(軽度の歯周病)
歯周病の初期段階では、歯ぐきが腫れて出血しやすくなります。この段階ではまだ痛みを感じることは少ないですが、歯ぐきが赤く腫れている、歯を磨くと出血する、といった症状が見られる場合は要注意です。
適切な歯磨きと定期的な歯科クリーニングを行うことで、歯肉炎は改善することができます。しかし、放置すると歯周病が進行し、痛みを感じるようになります。
・歯周炎(中等度の歯周病)
歯周病が進行すると、歯と歯ぐきの間の隙間(歯周ポケット)が深くなり、細菌が繁殖しやすくなります。この段階では、歯ぐきの腫れや痛みに加えて、口臭が気になることもあります。
また、歯がグラついたり、噛んだときに違和感を覚えることがあります。歯科医院では、スケーリング(歯石除去)やルートプレーニング(歯根のクリーニング)を行い、歯周病の進行を食い止めます。
・重度の歯周病(歯槽膿漏)
歯周病がさらに進行すると、歯を支える骨(歯槽骨)が溶けてしまい、歯が抜け落ちる危険性があります。この段階では、歯ぐきが大きく腫れ、膿が出ることもあります。
治療としては、歯周外科手術や、場合によっては抜歯が必要になることもあります。歯を失わないためにも、早めの受診が何よりも大切です。
知覚過敏:冷たいものや甘いものでしみる原因
歯が痛い原因は虫歯や歯周病だけではありません。知覚過敏によって歯がしみるような痛みを感じることもあります。知覚過敏は、歯の表面を覆うエナメル質がすり減ることで、象牙質が露出し、外部刺激に敏感になることで起こります。
・歯ぎしりや食いしばりによる影響
歯ぎしりや食いしばりが習慣化していると、歯の表面のエナメル質が削れ、知覚過敏を引き起こすことがあります。特に、ストレスによる無意識の食いしばりは、症状を悪化させる原因になります。
歯科医院では、ナイトガード(マウスピース)を装着することで、歯ぎしりによる負担を軽減することができます。
・過度なブラッシングによる影響
歯を強く磨きすぎると、歯ぐきが下がり、象牙質が露出することで知覚過敏が生じることがあります。
硬すぎる歯ブラシや強い力でのブラッシングを避け、やさしく丁寧に磨くことが大切です。
知覚過敏用の歯磨き粉を使用すると、歯の表面を保護し、しみる症状を緩和することができます。
・歯科治療後の一時的な知覚過敏
詰め物や被せ物をした後、一時的に知覚過敏の症状が出ることがあります。これは、治療による刺激で神経が過敏になっているためであり、多くの場合は時間とともに落ち着きます。
ただし、長期間しみる症状が続く場合は、詰め物の調整が必要な場合もあるため、歯科医院で相談するとよいでしょう。
歯の痛みの種類とその違いを知ろう

ズキズキ痛む場合(神経の炎症や虫歯の進行)
歯がズキズキと脈打つように痛む場合、多くは虫歯が神経まで進行していることが原因です。特に、何もしていないのに痛む場合は、歯の神経(歯髄)が炎症を起こしている可能性が高いです。この状態を「歯髄炎(しずいえん)」といい、早急な治療が必要になります。
・虫歯による歯髄炎
虫歯が象牙質を超えて神経に到達すると、炎症を引き起こします。初期のうちは冷たいものや甘いものがしみる程度ですが、進行すると何もしていなくてもズキズキと痛みを感じるようになります。特に、夜間に痛みが増すことが多いのが特徴です。
この状態になると、虫歯の進行がかなり進んでいるため、神経を取り除く「根管治療」が必要になります。放置すると炎症が広がり、膿が溜まる「根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)」へと進行し、さらに強い痛みや腫れを引き起こします。
・根尖性歯周炎(歯の根の先に膿が溜まる)
歯の神経が死んでしまった後、根の先に細菌感染が広がると、歯ぐきに膿が溜まり、腫れと痛みが生じることがあります。この状態では、噛むと強い痛みを感じたり、歯ぐきが腫れたりすることが多いです。
この場合も根管治療が必要になり、場合によっては外科的な処置が必要になることもあります。膿が大きくなると、顔が腫れることもあるため、早めに歯科医院を受診することが重要です。
・事故や強い衝撃による歯のダメージ
転倒や事故などで歯に強い衝撃が加わると、神経がダメージを受け、炎症を起こすことがあります。最初はそれほど痛みを感じなくても、時間が経つにつれて痛みが強くなることがあります。
歯が折れたり、ヒビが入っていたりする可能性もあるため、早めに歯科医院で診察を受けることが大切です。放置すると神経が壊死し、感染が広がる原因になります。
噛むと痛い場合(歯のひび割れや詰め物の問題)
噛むと痛みを感じる場合、歯や詰め物の問題が原因になっていることが多いです。
・歯のひび割れ(クラックトゥースシンドローム)
「クラックトゥースシンドローム」とは、歯に小さなひび(クラック)が入ることで、噛むたびに痛みを感じる状態を指します。歯ぎしりや強い噛みしめが原因で発生することが多く、特に奥歯に多く見られます。
この状態では、レントゲンでは異常が見つかりにくいため、歯科医師による慎重な診断が必要です。軽度のひびであれば、詰め物や被せ物で補強することで改善できますが、ひびが深く進行している場合は、抜歯が必要になることもあります。
・詰め物・被せ物の不具合
以前に治療した詰め物や被せ物が、時間とともに劣化すると、噛んだときに違和感や痛みを感じることがあります。詰め物が浮いていたり、隙間ができていたりすると、その部分に細菌が侵入し、再び虫歯になることもあります。
この場合、詰め物を新しいものに交換することで改善することができます。ただし、虫歯が進行している場合は、根管治療が必要になることもあります。
・噛み合わせの問題(歯ぎしりや食いしばり)
無意識の歯ぎしりや食いしばりが原因で、歯に過度な負担がかかると、噛んだときに痛みを感じることがあります。特に、ストレスが原因で歯ぎしりをする人は、症状が悪化しやすいです。
この場合、ナイトガード(歯ぎしり防止用のマウスピース)を装着することで、歯への負担を軽減し、痛みを予防することができます。
持続的に違和感がある場合(根の炎症や歯周病)
歯がズキズキ痛むわけではないものの、違和感や鈍い痛みが続く場合、歯の根の炎症や歯周病が関係していることが多いです。
・慢性的な根の炎症
虫歯や外傷によって神経が死んだ歯は、細菌感染が進行し、歯の根の周囲に慢性的な炎症を引き起こすことがあります。
症状としては、「押すと違和感がある」「たまに鈍い痛みを感じる」「噛むと軽く痛む」といったものが見られます。
この状態が続くと、炎症が悪化し、膿が溜まることもあるため、根管治療が必要になることがあります。
・歯周病による歯の動揺
歯周病が進行すると、歯を支える骨が溶けてしまい、歯がグラグラするようになります。
これにより、食事の際に違和感を感じたり、噛むと軽い痛みを感じることがあります。
歯周病は進行するほど治療が難しくなるため、早めに歯科医院でクリーニングや歯周病治療を受けることが重要です。
・親知らずの影響
親知らずが生えてくる途中で周囲の歯を押したり、炎症を起こしたりすると、持続的な違和感や鈍い痛みを感じることがあります。
特に、親知らずが横向きに生えている場合は、隣の歯を圧迫し、噛み合わせにも影響を与えることがあります。
この場合、痛みが続くようなら抜歯を検討する必要があります。
親知らずの状態によっては、経過観察だけで済むこともあるため、歯科医院で診察を受けることが大切です。
痛みがひどいときに自宅でできる応急処置

市販の痛み止めを正しく使う方法
歯の痛みが強くなったとき、すぐに歯科医院へ行けない場合もあります。その際、痛みを一時的に和らげる方法として、市販の痛み止め(鎮痛剤)を正しく活用することが重要です。
・痛み止めの種類と適切な使用方法
市販の鎮痛剤にはいくつかの種類がありますが、歯の痛みに効果的なものとして以下が挙げられます。
- アセトアミノフェン系(例:タイレノール)
比較的穏やかな作用で、小児や妊婦も使用しやすい。
炎症を抑える効果は弱いため、強い腫れがある場合は別の鎮痛剤が有効。 - 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)(例:ロキソニン、イブプロフェン)
炎症を抑える効果があり、ズキズキとした強い痛みにも有効。
胃に負担がかかることがあるため、空腹時の服用は避ける。
服用する際は、用法・用量を守り、決められた時間間隔を空けることが大切です。痛みがひどくても、自己判断で過剰摂取しないよう注意しましょう。
・鎮痛剤を服用しても痛みが取れない場合の対策
鎮痛剤を服用しても痛みが治まらない場合、以下のような原因が考えられます。
- 炎症が進行し、膿が溜まっている
- 神経が強く刺激され、鎮痛剤では抑えきれない状態になっている
- 痛みの原因が歯ではなく、別の病気によるもの(副鼻腔炎や顎関節症など)
鎮痛剤で痛みを一時的に和らげたとしても、根本的な治療にはなりません。痛みが続く場合は、できるだけ早く歯科医院を受診することが必要です。
冷やすべき?温めるべき?痛みを悪化させない対処法
歯の痛みがひどいとき、患部を冷やすべきか温めるべきか迷うことがあります。状況によって適切な対応が異なるため、痛みの原因に応じた対処が重要です。
・冷やしたほうが良いケース
以下のような症状がある場合は、患部を冷やすことで痛みが和らぐことがあります。
- 歯ぐきが腫れている場合(炎症による腫れ)
- 親知らずが腫れている場合
- 根尖性歯周炎(歯の根の先に膿が溜まっている状態)
冷やす方法として、保冷剤や氷をタオルで包み、頬の外側から10〜15分程度当てると、腫れや痛みを軽減できます。ただし、長時間冷やし続けると血流が悪くなり逆効果になるため、適度に休憩を入れながら冷やすことが大切です。
・温めると悪化するケース
歯の痛みがあるときに、温めると逆に症状が悪化することがあります。特に、膿が溜まっている状態(根尖性歯周炎や歯ぐきの腫れ)では、血流が増加し、炎症が広がる可能性があるため温めるのはNGです。
一方で、噛み締めや顎のこわばりが原因の痛み(顎関節症など)の場合は、温めることで筋肉がほぐれ、症状が改善することがあります。
この場合は、温かいタオルを使って顎をリラックスさせるとよいでしょう。
うがいはNG?正しい口腔ケアの仕方
歯の痛みがあると、うがいをして清潔に保ちたくなることがありますが、痛みの原因によっては、うがいが逆効果になることもあります。正しい口腔ケアの仕方を知り、症状を悪化させないよう注意しましょう。
・うがいが有効なケース
以下のような場合は、ぬるま湯や殺菌作用のある洗口液でやさしくうがいをすることで症状の緩和が期待できます。
- 歯周病や親知らずの炎症が原因の痛み
- 食べかすが挟まって痛みが出ている場合
- 手術後や抜歯後のケアとして
ただし、強くうがいをしすぎると、かえって炎症を悪化させたり、傷口を刺激してしまう可能性があるため、優しくゆすぐことを意識しましょう。
・うがいがNGなケース
以下のような場合は、うがいをすると痛みが悪化する可能性があるため、注意が必要です。
- 虫歯の神経が露出している場合
冷たい水や強い刺激が加わると、痛みが増すことがあります。
できるだけ刺激を避け、歯科医院での治療を優先しましょう。 - 抜歯後の傷が治る前
抜歯直後に強いうがいをすると、血の塊(血餅)が剥がれ、傷口の治癒が遅くなる可能性があります。
24時間は強いうがいを避け、歯科医の指示に従いましょう。
・正しい歯磨きの方法
歯が痛いときは、歯磨きを怠りがちですが、口腔内を清潔に保つことは痛みの軽減につながります。
- 痛みがある部分はやさしく磨く(強く磨くと痛みが悪化することがある)
- フッ素入りの歯磨き粉を使用する(知覚過敏や虫歯の痛みの軽減に効果的)
- 歯間ブラシやデンタルフロスで汚れを取り除く(痛みがある場合は慎重に使用)
適切なケアを行うことで、痛みが和らぎ、治療までの間に症状を悪化させるのを防ぐことができます。
歯科医院で受けられる治療とは?

虫歯治療:削る治療から根管治療まで
虫歯の進行度によって、治療方法は異なります。初期段階では簡単な処置で済むことが多いですが、進行すると神経を取る処置(根管治療)や抜歯が必要になることもあります。
・初期の虫歯(C1・C2)の治療
虫歯がエナメル質や象牙質にとどまっている段階では、削る量を最小限に抑えた治療が可能です。
- コンポジットレジン修復(ダイレクトボンディング)
虫歯を削った部分に白い樹脂を詰める治療。
見た目が自然で、比較的短時間で治療が完了する。
保険適用されるケースが多い。 - フッ素塗布(初期虫歯の場合)
虫歯の初期段階であれば、削らずにフッ素塗布で進行を防ぐことができる。
ただし、痛みを感じる段階まで進行している場合は、早めの治療が必要。
・進行した虫歯(C3)の治療(根管治療)
虫歯が神経(歯髄)に達すると、歯の内部の炎症が進行し、ズキズキとした痛みを伴うことが多くなります。この場合、根管治療(歯の神経を取り除く治療)が必要になります。
- 根管治療の流れ
- 虫歯が進行した部分を削り、歯の神経を除去。
- 根管内を洗浄・消毒し、薬剤を詰める。
- 最終的に詰め物や被せ物を装着し、歯を補強する。
根管治療を適切に行うことで、抜歯をせずに歯を残すことが可能になります。ただし、治療期間が長くなるため、定期的な通院が必要です。
・末期の虫歯(C4)の治療(抜歯とその後の選択肢)
虫歯が重度に進行し、歯の根まで崩壊してしまった場合、歯を残すことが難しくなり、抜歯が選択されることがあります。
- 抜歯後の治療選択肢
- インプラント:人工の歯根を埋め込んで歯を補う方法。自然な見た目と噛む力が再現できるが、外科手術が必要。
- ブリッジ:隣の歯を削って人工歯を橋渡しする方法。見た目が自然だが、健康な歯への負担が増す。
- 入れ歯(義歯):比較的安価で治療期間も短いが、違和感が出ることがある。
抜歯後の治療は、それぞれのライフスタイルや健康状態に応じて選択することが重要です。
歯周病治療:炎症を抑えるクリーニングや外科的処置
歯周病は、進行すると歯を支える骨が溶け、最終的には歯を失うリスクが高まります。早期発見・早期治療が重要で、症状に応じた治療が行われます。
・軽度の歯周病(歯肉炎)の治療
- スケーリング(歯石除去)
歯ぐきの炎症を抑えるために、歯の表面に付着した歯石を除去する処置。
定期的に受けることで、歯周病の進行を防ぐことができる。 - 適切なブラッシング指導
歯周病の原因となるプラーク(歯垢)の除去が不十分だと、炎症が悪化するため、正しい歯磨きの方法を学ぶことが重要。
・中等度の歯周病(歯周炎)の治療
- ルートプレーニング(歯根のクリーニング)
歯周ポケットが深くなっている場合、歯の根に付着した歯石や細菌を除去する処置を行う。
歯ぐきの炎症が軽減され、歯のぐらつきを抑えることができる。 - 抗菌療法
炎症が強い場合、抗生物質の投与や薬剤を使った歯周ポケットの洗浄を行うことがある。
・重度の歯周病(歯槽膿漏)の治療
- 歯周外科治療
歯周ポケットが深く、通常のクリーニングでは対応できない場合、外科的に歯ぐきを剥がして歯根を清掃する手術を行う。
失われた骨を再生するための再生療法(GTR法やエムドゲインなど)が適用されることもある。 - 抜歯
歯周病が進行し、歯を支える骨がほとんど残っていない場合、最終的に抜歯が必要になることもある。
歯周病は自覚症状が少ないまま進行することが多いため、早期発見・早期治療が重要です。定期的な歯科検診を受けることで、進行を防ぐことができます。
詰め物・被せ物の修復:歯の破損や噛み合わせの改善
歯の詰め物や被せ物が原因で痛みが生じることがあります。適切な修復を行うことで、快適な噛み合わせを維持し、歯を長く健康に保つことができます。
・詰め物の交換(セメントの劣化や隙間の発生)
古い詰め物が劣化すると、隙間から細菌が侵入し、二次虫歯のリスクが高まる。
詰め物の交換を行い、虫歯の再発を防ぐ。
・被せ物(クラウン)の調整や再装着
被せ物が合っていないと、噛み合わせの違和感や歯ぐきの炎症を引き起こす。
被せ物を再調整することで、快適な噛み合わせを取り戻すことができる。
・噛み合わせの調整
長年の噛み癖や歯ぎしりによって、歯に負担がかかることがある。
必要に応じてナイトガード(マウスピース)を使用し、歯を保護する。
「痛みがない=治った」は間違い?

神経が死んでしまった場合の痛みの消失
歯が激しく痛んでいたのに、ある日突然痛みが消えた…。これは決して「治った」わけではなく、むしろ症状が悪化しているサインである可能性があります。その理由の一つが、歯の神経(歯髄)が壊死してしまったことです。
・虫歯が進行し、神経が壊死する流れ
- 初期の虫歯では、冷たいものや甘いものがしみる程度の痛みを感じます。
- 進行すると、歯の神経に炎症が起こり、ズキズキと強い痛みが生じます。
- さらに放置すると、炎症が進んで神経が壊死し、痛みを感じなくなります。
この段階になると、歯の内部では細菌感染が進んでおり、歯の根(根尖部)に膿がたまるリスクが高まります。「痛くなくなったから大丈夫」と思って放置すると、顎の骨まで炎症が広がり、最終的には抜歯が必要になることもあります。
・神経が死んだ歯はどうなる?
- 根尖性歯周炎(歯の根に膿がたまる)
神経が死んでしまった歯は、細菌の温床になりやすく、歯の根の先に膿がたまることがあります。
症状が進むと、歯ぐきが腫れたり、噛んだときに痛みを感じるようになります。 - 歯の変色
神経が死んだ歯は、時間が経つと黒っぽく変色することがあります。これは、歯の内部に血液やタンパク質が残ることで起こる現象です。 - 最悪の場合、抜歯が必要に
根管治療で感染を取り除くことができない場合、抜歯が必要になることがあります。
抜歯をすると、インプラント・ブリッジ・入れ歯などの治療が必要になります。
・神経が死んでも早めの治療で歯を残せる
神経が死んだ歯でも、早期に治療すれば抜歯を回避できる可能性があります。根管治療によって歯の内部の感染を取り除き、適切な修復を行うことで、歯を長く使い続けることができます。
「痛みが消えた=治った」ではなく、むしろ「症状が進行しているサイン」と認識し、すぐに歯科医院を受診することが大切です。
自然治癒しない歯の病気とは?
歯や歯ぐきの病気は、放置しても自然に治ることはありません。皮膚の傷や軽い風邪なら自己治癒力で回復することもありますが、歯は一度ダメージを受けると、何もしなければ悪化する一方です。
・虫歯は自然に治らない
初期の虫歯(C1)ならフッ素で進行を遅らせることができますが、すでに穴があいてしまった虫歯は、治療しない限り進行を止めることはできません。
「削らない治療(ドックスベストセメントなど)」もありますが、完全に虫歯が治るわけではなく、適切な治療が必要です。
・歯周病も進行するだけ
歯周病は「サイレントディジーズ(静かなる病気)」とも呼ばれ、痛みを感じにくいまま進行します。
初期段階(歯肉炎)ではブラッシングや歯科医院でのクリーニングで改善できますが、中等度~重度になると歯を支える骨が溶けてしまい、元に戻ることはありません。
進行すればするほど、治療の選択肢が限られてしまうため、早期治療が重要です。
・親知らずの痛みも放置NG
親知らずの痛みは、周囲の歯ぐきの炎症(智歯周囲炎)が原因になっていることが多いです。
「痛みがなくなったから大丈夫」と放置すると、炎症が再発しやすくなり、最終的に腫れや発熱を伴うこともあります。
予防的な抜歯や、定期的なクリーニングでリスクを減らすことが大切です。
痛みがなくても定期検診が必要な理由
「痛みがないから歯医者に行く必要はない」と思っている方も多いですが、定期的な歯科検診を受けることで、痛みが出る前に問題を発見し、予防することができます。
・痛みが出る頃には病気が進行している
虫歯も歯周病も、初期段階ではほとんど自覚症状がありません。
例えば、歯周病は自覚症状のないまま進行し、気づいたときには歯を支える骨が溶けてしまっていることもあります。
「痛くなったら行く」ではなく、「痛くなる前に予防する」という意識が大切です。
・予防処置を受けることで健康な歯を維持できる
定期検診では、以下のような予防処置を受けることができます。
- 歯のクリーニング(スケーリング):歯石を除去し、歯周病を予防する。
- フッ素塗布:虫歯になりやすい部分を強化する。
- 噛み合わせチェック:歯ぎしりや食いしばりがないか確認し、必要に応じてマウスピースを作成。
これらの処置を受けることで、痛みを感じる前に問題を防ぐことが可能になります。
・将来的な治療費を抑えることができる
早期に虫歯や歯周病を発見すれば、簡単な治療で済み、治療費も抑えられます。
逆に、進行してしまうと根管治療や抜歯、インプラント治療が必要になり、治療費が高額になる可能性があります。
「定期検診で少しのコストをかける」ことが、「将来的な高額な治療を防ぐ」ことにつながります。
歯の痛みを予防するためにできること

正しい歯磨き習慣と歯間ケアの重要性
毎日の歯磨きは、歯の健康を維持するための最も基本的なケアです。しかし、間違った磨き方をしていると、虫歯や歯周病のリスクが高まり、結果的に歯の痛みを引き起こす原因になります。
・正しい歯磨きのポイント
- 歯ブラシの持ち方
力を入れすぎると歯ぐきを傷つけるため、鉛筆を持つように軽く握るのが理想的。
硬い歯ブラシではなく、やや柔らかめのブラシを選ぶことで歯や歯ぐきへの負担を軽減できる。 - ブラッシングの基本
小刻みに動かす:ゴシゴシと力を入れて磨くのではなく、1本1本丁寧に磨くことが大切。
歯と歯ぐきの境目を意識する:歯周病予防には、歯と歯ぐきの間のプラーク(歯垢)をしっかり落とすことが重要。
1日2〜3回、1回3分以上を目安に:特に寝る前の歯磨きはしっかり行うことが大切。 - 歯磨き粉の選び方
フッ素配合のものを使用することで、虫歯の発生を防ぎやすくなる。
知覚過敏がある場合は、知覚過敏専用の歯磨き粉を使用すると痛みを軽減できる。
・歯間ケアの重要性
歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れ(プラーク)の約40%しか除去できないとされています。そのため、歯間ケアを習慣化することが歯の痛みを防ぐために不可欠です。
- デンタルフロス(糸ようじ)
虫歯や歯周病ができやすい歯と歯の間の汚れを取り除くのに最適。
特に奥歯の隙間は汚れが溜まりやすいため、意識してフロスを通すのが重要。 - 歯間ブラシ
ブラシのサイズを歯の隙間に合わせて選ぶことで、歯ぐきを傷つけずに汚れを効果的に除去できる。
歯周病予防にも効果的なため、特に歯ぐきが下がり気味の人にはおすすめ。
歯間ケアを歯磨き後の習慣として取り入れることで、虫歯や歯周病のリスクを大幅に減らすことができます。
予防歯科のススメ:定期検診で早期発見
歯の痛みを未然に防ぐためには、予防歯科を積極的に活用することが大切です。定期検診を受けることで、痛みを感じる前に問題を発見し、適切な処置を受けることができます。
・定期検診の頻度
一般的に、3〜6ヶ月に1回のペースで歯科検診を受けることが推奨されています。しかし、以下のような人は、より短い間隔(3ヶ月ごと)での受診がおすすめです。
- 虫歯になりやすい人(以前に虫歯の治療歴が多い)
- 歯周病のリスクが高い人(歯ぐきの腫れや出血がある)
- 矯正治療を受けている人(装置の影響で歯磨きがしにくい)
・定期検診で受けられる主なケア
- 歯のクリーニング(スケーリング)
歯ブラシでは落としきれない歯石を除去し、歯周病の進行を防ぐ。
歯ぐきの健康状態をチェックし、必要に応じて歯周病治療を行う。 - フッ素塗布
虫歯の発生を抑える効果があり、特に虫歯リスクが高い人には有効。
歯の表面を強化し、知覚過敏の予防にも役立つ。 - 噛み合わせチェック
噛み合わせが悪いと、特定の歯に負担がかかり、歯の痛みや顎関節症の原因になることがある。
必要に応じて、ナイトガード(マウスピース)を作成し、歯ぎしりや食いしばりを予防する。
定期検診を受けることで、痛みが出る前にトラブルを未然に防ぐことができ、将来的な治療費や時間の負担を減らすことができます。
生活習慣と食事が歯に与える影響
毎日の食生活や生活習慣も、歯の健康に大きく影響します。特に虫歯や歯周病の予防には、食事の内容や食べ方に注意することが重要です。
・虫歯になりやすい食べ物・なりにくい食べ物
- 虫歯になりやすい食品
- 砂糖を多く含む食品(お菓子、ジュース):糖分が口内の細菌と結びつき、酸を発生させる原因に。
- 粘着性の高い食品(キャラメル、グミなど):歯に長時間くっつきやすく、虫歯のリスクを高める。
- 歯に良い食品
- カルシウムを多く含む食品(乳製品、魚、大豆製品):歯の再石灰化を助け、エナメル質を強化する。
- 繊維質の多い食品(野菜、果物):噛む回数が増え、唾液の分泌を促すことで口内を浄化する効果がある。
・間食の摂り方に注意
- ダラダラ食べを避ける:長時間食べ続けると、口の中が酸性の状態になり、虫歯になりやすくなる。
- 食後はすぐに水で口をゆすぐ:食後に軽くうがいをすることで、酸を中和しやすくなる。
・睡眠とストレス管理も歯の健康に影響
- ストレスが溜まると、歯ぎしりや食いしばりが増え、歯に負担がかかる。
- 睡眠不足は免疫力を低下させ、歯周病の悪化につながることもある。
生活習慣を見直すことで、歯の健康を維持し、痛みの発生を防ぐことができます。
歯が痛くならないためのセルフチェックポイント

・毎日の口腔ケアで意識すべきこと
歯の痛みを未然に防ぐためには、日々のセルフケアが最も重要です。しかし、自己流の歯磨きやケアでは、十分に汚れが落ちていないこともあります。正しいケアを習慣化し、歯の健康を守るために意識すべきポイントを確認しましょう。
・歯磨きの質を高める
- 1日2〜3回、1回3分以上を目安にしっかり磨く
- 特に就寝前の歯磨きは重要。夜間は唾液の分泌が減るため、口内環境が悪化しやすく、細菌が増殖しやすくなります。
- 歯と歯ぐきの境目を意識して磨く
- 歯ブラシを45度の角度で当て、小刻みに動かして汚れを取り除く。
- デンタルフロス・歯間ブラシの活用
・口内の乾燥を防ぐ
- 唾液には虫歯や歯周病を防ぐ作用があり、口内を常に潤った状態に保つことが大切。
- 水分補給をこまめに行う(特に寝る前や起床後は口が乾燥しやすいため、水を飲む習慣をつける)。
- 口呼吸ではなく、鼻呼吸を意識する(口呼吸は口内を乾燥させ、細菌の繁殖を促す)。
・歯ぐきの状態を定期的にチェック
- 歯磨きの際に出血していないか?
- 歯ぐきが腫れていないか?
- 赤く腫れていたり、触ると痛みがある場合は、歯周病の初期症状の可能性がある。
これらのポイントを毎日意識することで、虫歯や歯周病のリスクを大幅に低減することができます。
こんな症状があったら要注意!早めの受診が必要なサイン
・歯がしみる(冷たい・甘いものが刺激になる)
初期の虫歯、知覚過敏の可能性。
原因の特定が必要なため、放置せずに歯科医院で検査を受けることが重要。
・口臭が気になる
口臭は歯周病、虫歯の進行、舌の汚れが原因となっていることが多い。
歯ぐきの腫れや出血がある場合は、歯周病が進行している可能性が高い。
・歯ぐきが下がってきた
歯ぐきが下がると、歯の根元が露出し、知覚過敏や虫歯のリスクが高まる。
歯周病が進行している可能性があるため、早めの対応が必要。
歯ぎしりや噛み合わせが原因の痛みとは?
歯の痛みの原因は虫歯や歯周病だけではなく、噛み合わせの問題や歯ぎしりによっても引き起こされることがあります。これらの症状は、意識しにくいため、自覚がないまま進行するケースが多いです。
・歯ぎしり・食いしばりによるダメージ
- 無意識の歯ぎしりが、歯に過度な負担をかける
- 歯ぎしりを続けることで、歯がすり減ったり、ヒビが入ったりすることがある。
- 朝起きたときに顎が疲れている場合は、睡眠中に食いしばっている可能性が高い。
- 対策:ナイトガード(マウスピース)の使用
・噛み合わせのズレによる痛み
歯並びや詰め物・被せ物の高さが合っていないと、特定の歯に負担が集中する。
その結果、歯の痛みや顎関節症の原因になることがある。
・顎関節症の影響
- 顎関節症が進行すると、顎の痛みだけでなく、歯の痛みとして感じることもある。
- 症状:口を開閉すると「カクッ」と音がする、口を大きく開けづらい。
- 対策:硬い食べ物を避け、顎に負担をかけないようにする。
歯ぎしりや噛み合わせの問題は、長期間放置すると歯の痛みが慢性化しやすいため、早めに専門的な診断を受けることが重要です。
痛みが取れない場合に考えられる他の疾患

親知らずの影響:抜くべき?経過観察すべき?
親知らず(第三大臼歯)は、生え方や周囲の状態によって、歯の痛みや炎症を引き起こす原因になることがあります。親知らずの影響で痛みが取れない場合、抜歯すべきか経過観察すべきかを適切に判断することが重要です。
・親知らずが原因で痛みが出るケース
- 歯ぐきの腫れや痛みがある(智歯周囲炎)
親知らずが部分的にしか生えていない場合、その周囲に細菌が溜まりやすく、炎症を起こすことがあります。
特に、疲れやストレスが溜まっているときに炎症が悪化しやすいのが特徴です。 - 隣の歯を押している(歯列の乱れを引き起こす)
横向きや斜めに生えている親知らずが、隣の歯を圧迫し、歯の痛みや噛み合わせの問題を引き起こすことがあります。 - 虫歯になりやすい(親知らずが磨きにくい)
口の奥にあるため、歯ブラシが届きにくく、虫歯や歯周病になりやすい。
親知らず自体が虫歯になるだけでなく、隣の歯まで虫歯になるリスクが高いのが問題です。
・親知らずを抜くべきケース
- 強い痛みや腫れを繰り返している(智歯周囲炎が頻繁に起こる場合)。
- 親知らずが斜め・横向きに生えており、歯列を乱したり隣の歯に悪影響を与える場合。
- 親知らずが完全に機能しておらず、しっかり噛むことができない場合。
・経過観察するべきケース
- まっすぐ生えていて、噛み合わせに問題がない場合。
- 腫れや痛みがなく、問題を起こしていない場合(定期的な歯科医院でのチェックが必要)。
親知らずの状態は個人差があるため、歯科医院でレントゲン撮影を行い、適切な判断を仰ぐことが最も確実な方法です。
歯以外の原因:副鼻腔炎や顎関節症の可能性
歯の痛みが続く場合、実は歯に原因がないケースもあります。特に、副鼻腔炎や顎関節症などの病気が、歯の痛みとして現れることがあります。
・副鼻腔炎(蓄膿症)による歯の痛み
副鼻腔炎とは、鼻の奥にある副鼻腔という空洞に炎症が起こる病気です。
特徴: 上の奥歯(特に6番・7番)が痛むことがあり、虫歯と間違えやすい。
その他の症状: 鼻づまり、顔の圧迫感、黄色い鼻水が出る。
- 対処法:
- 耳鼻科での診察を受ける(抗生物質や鼻洗浄などで治療を行う)。
- 歯科医院で歯の状態もチェックし、虫歯や歯周病がないか確認する。
・顎関節症による痛み
顎のズレや筋肉の緊張が、歯の痛みとして感じられることがあります。
- 症状:
- 口を開閉すると「カクッ」と音がする。
- 顎が痛い、こわばる感じがする。
- 朝起きたときに歯が痛い(無意識の食いしばりが原因)。
- 対処法:
- 歯科医院での噛み合わせチェックを受ける。
- 必要に応じてナイトガード(マウスピース)を装着し、顎の負担を軽減する。
・神経性の痛み(非歯原性歯痛)
歯そのものには問題がないのに、痛みが続くケース。
- 三叉神経痛(顔の神経の異常)が原因で、歯が痛むことがある。
- 特徴: 電気が走るような鋭い痛みを感じる。
- 対処法:
- 歯科医院で検査を受け、歯に問題がない場合は神経内科や口腔外科で診察を受ける。
歯の痛みが長引く場合、単なる虫歯や歯周病ではなく、他の病気が隠れている可能性があるため、自己判断せずに専門医の診察を受けることが重要です。
ストレスが引き起こす歯の痛みとは?
ストレスが歯の痛みに影響を与えることがあります。特に、無意識の食いしばりや歯ぎしりが、歯や顎に負担をかける原因となります。
・ストレスによる食いしばり・歯ぎしり
- 日中の緊張やストレスにより、無意識に歯を食いしばっていることがある。
- 就寝中の歯ぎしりも、歯に大きな負担をかけ、痛みの原因になる。
- 特に、ストレスが強いと、歯ぎしりの頻度が増え、歯のすり減りや知覚過敏を引き起こすこともある。
・自律神経の乱れによる口内トラブル
- ストレスが原因で自律神経が乱れると、唾液の分泌が減少し、口内環境が悪化する。
- その結果、虫歯や歯周病が進行しやすくなる。
・ストレス緩和のための対策
- リラックスする時間を持つ(深呼吸、ストレッチなど)。
- 就寝時にナイトガードを装着し、歯ぎしりを防ぐ。
- 歯科医院で噛み合わせのチェックを受け、必要に応じて調整を行う。
歯の痛みを感じたらすぐに受診を!

早期治療の重要性と予防の大切さ
歯の痛みを感じたとき、多くの人は「少し様子を見よう」「時間が経てば治るかもしれない」と考えがちですが、歯の痛みの原因となる疾患は自然に治ることはほぼありません。
早期に治療を受けることで、痛みを最小限に抑え、歯の寿命を延ばすことができます。
・早期治療のメリット
- 治療の負担が軽減される
初期の虫歯なら、簡単な詰め物(レジン修復)だけで治療できる。
進行すると、神経を取る根管治療や抜歯が必要になり、治療期間も長くなる。 - 治療費を抑えられる
早めの治療なら、小さな処置で済むため、治療費の負担も軽くなる。
進行すると、根管治療やインプラント治療など高額な治療が必要になる可能性が高まる。 - 歯の寿命を延ばせる
一度削った歯や神経を取った歯は、健康な歯に比べて寿命が短くなる。
早期治療でダメージを最小限に抑えることが、生涯自分の歯を維持するために重要。
・治療を先延ばしにするリスク
- 痛みが悪化し、生活に支障が出る
痛みがひどくなると、仕事や睡眠にも影響を与え、集中力の低下やストレスの原因になる。 - 細菌感染が広がり、全身の健康に影響を及ぼす
進行した虫歯や歯周病が原因で、細菌が血管を通じて全身に広がることがある(敗血症のリスク)。
糖尿病や心疾患と歯周病には関連があることが研究で明らかになっており、歯の健康は全身の健康にも直結している。 - 歯を失うリスクが高まる
進行すると、抜歯が必要になるケースが増える。
抜歯後の治療(インプラント・ブリッジ・入れ歯)は、天然の歯に比べて違和感があり、費用もかかる。
・定期検診で痛みが出る前に予防する
- 3〜6ヶ月に1回の定期検診を受けることで、痛みが出る前に異常を発見し、簡単な処置で済ませることができる。
- 歯のクリーニングやフッ素塗布を受けることで、虫歯や歯周病の予防が可能。
- 噛み合わせチェックやナイトガードの作成を行い、歯ぎしりや食いしばりによる負担を軽減することができる。
「痛くなったら行く」のではなく、「痛くなる前に予防する」意識を持つことが、健康な歯を守る鍵となります。
痛みがあるときに避けるべき行動とは?
歯が痛いとき、誤った対処をすると症状を悪化させてしまう可能性があります。痛みを和らげるために、避けるべき行動を理解しておくことが大切です。
・熱いもの・冷たいものの摂取を避ける
知覚過敏や虫歯がある場合、冷たいもの・熱いものが刺激となり、痛みが増すことがある。
特に神経に近い部分まで進行した虫歯では、温度変化に敏感になっているため注意が必要。
・強いうがいをしない
痛みがあるからといって強くうがいをしすぎると、炎症を悪化させる可能性がある。
特に抜歯後などは、強いうがいで血餅(傷を塞ぐ血の塊)が取れてしまい、治りが遅くなることがある。
・患部を温めない
「痛いところを温めたほうがよい」と思われがちだが、炎症がある場合は逆効果。
温めることで血流が増え、腫れや痛みが悪化することがある。
炎症が原因の痛みには、冷やすことで腫れを抑えるほうが効果的な場合が多い。
・自己判断で市販薬を飲み続けない
鎮痛剤は一時的に痛みを抑えるだけであり、根本的な治療にはならない。
痛み止めを飲み続けることで、病気の進行を見逃してしまう可能性がある。
「痛みがなくなったから大丈夫」と思わず、必ず歯科医院で診察を受けることが大切。
歯科医院での定期的なメンテナンスのすすめ
歯の痛みを予防し、健康な口内環境を維持するためには、歯科医院での定期的なメンテナンスが不可欠です。
・定期検診のメリット
- 虫歯や歯周病の早期発見が可能
初期段階で発見すれば、治療の負担が最小限で済む。 - プロフェッショナルケアを受けられる
歯石の除去(スケーリング)により、歯周病の進行を防げる。
フッ素塗布で歯の再石灰化を促し、虫歯予防ができる。 - 歯のトラブルを未然に防ぐ
噛み合わせのチェックを行い、異常があれば早めに対応できる。
歯ぎしり・食いしばりがある場合、ナイトガード(マウスピース)を作成し、歯を保護できる。
・どのくらいの頻度で受診すべきか?
- 一般的には3〜6ヶ月に1回の定期検診が推奨される。
- 虫歯や歯周病のリスクが高い人は、3ヶ月ごとに受診するのが理想。
- 矯正治療中の人やインプラントを入れている人も、定期的なチェックが重要。
「治療のために通う」のではなく、「健康を維持するために通う」意識を持つことが大切です。
監修:青山一丁目 麻布歯科
所在地〒:東京都港区赤坂8-5-32 田中駒ビル1F
電話番号☎:03-6434-9877
*監修者
青山一丁目 麻布歯科
ドクター 安達 英一
*出身大学
日本大学歯学部
*経歴
・日本大学歯学部付属歯科病院 勤務
・東京都式根島歯科診療所 勤務
・長崎県澤本歯科医院 勤務
・医療法人社団東杏会丸ビル歯科 勤務
・愛育クリニック麻布歯科ユニット 開設
・愛育幼稚園 校医
・愛育養護学校 校医
・青山一丁目麻布歯科 開設
・区立西麻布保育園 園医
*所属
・日本歯科医師会
・東京都歯科医師会
・東京都港区麻布赤坂歯科医師会
・日本歯周病学会
・日本小児歯科学会
・日本歯科審美学会
・日本口腔インプラント学会
投稿日:2025年2月28日