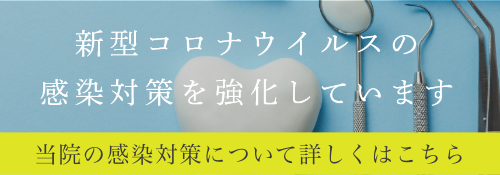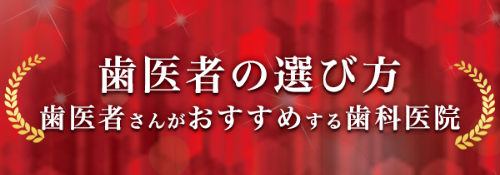歯ぎしりとは?無意識に起こる歯と顎のダメージ

・歯ぎしりの種類:グラインディング・クレンチング・タッピング
一口に「歯ぎしり」といっても、実はその動きにはいくつかのタイプが存在します。代表的なものが「グラインディング」「クレンチング」「タッピング」の3種類です。グラインディングは上下の歯を強くすり合わせる動きで、もっとも一般的な歯ぎしりです。この動きは就寝中に多く見られ、ギリギリと不快な音を立てるのが特徴です。クレンチングは歯をギュッと強く噛みしめるタイプで、音が出にくいため自覚されにくいものの、歯や顎関節への負担が非常に大きいとされています。最後に、タッピングは上下の歯を小刻みにカチカチと打ち合わせるような動きで、比較的稀ではありますが、神経の過敏さやストレスの影響が関係していると考えられています。これらの歯ぎしりはいずれも無意識下で行われることが多く、長期間にわたって継続することで歯や顎に大きなダメージを与える可能性があります。
・起きている間も?日中の歯ぎしりに注意
歯ぎしりは寝ている間だけの現象だと思われがちですが、実は日中にも無意識のうちに歯を噛みしめたり食いしばったりしている人が少なくありません。これを「覚醒時ブラキシズム」と呼び、仕事中の集中時やスマートフォンを操作しているとき、運動中などに頻繁に見られます。日中の歯ぎしりは音が出ないため、周囲はもちろん本人も気づかないまま続けてしまうことが多いのです。特にデスクワークや緊張を強いられる場面では、自然と奥歯に力が入り、咀嚼筋に常に緊張がかかった状態が続きます。これが習慣化すると、顎関節への負担や歯の摩耗、歯ぐきのダメージにつながるリスクが高まります。
覚醒時の歯ぎしり対策としては、自分がどのような場面で無意識に噛みしめているかを意識し、「上下の歯を離しておくこと」を習慣づける意識行動が重要です。専門的な治療に入る前に、日常での意識改革が予防への第一歩になります。
・どうして無意識でやってしまうのか
歯ぎしりが無意識下で起こるのは、主に中枢神経の活動や自律神経の影響によるものとされています。特に就寝中の歯ぎしりは、「ノンレム睡眠」と呼ばれる深い睡眠中に頻発し、睡眠の質やサイクルとも密接に関係しています。睡眠中に交感神経が過剰に働いていると、筋肉の緊張が高まり、噛みしめや歯ぎしりといった行動が無意識に引き起こされるのです。また、精神的なストレスや不安が歯ぎしりの誘因となることもよくあります。日中に受けた緊張や疲労が、睡眠中に筋活動として現れるというわけです。さらに、噛み合わせの不調や顎関節のズレ、鼻づまりなどの呼吸障害も、歯ぎしりの原因となることがあります。つまり、歯ぎしりは単なる癖ではなく、神経系・筋肉系・心理的要因・構造的要因が複雑に絡み合った現象であり、自己判断だけで原因を特定するのは困難です。症状が続く場合は、歯科での総合的な評価を受けることが重要です。
ストレスだけじゃない?歯ぎしりの主な原因

・精神的ストレスと交感神経の関係
歯ぎしりの最大の要因として知られているのが「ストレス」です。私たちの身体は精神的ストレスを感じると、自律神経のうち交感神経が優位になります。交感神経が活発になると筋肉は緊張状態となり、それが就寝中の歯ぎしりや日中の食いしばりにつながるのです。とくに現代社会では、仕事や人間関係、生活環境の変化などで慢性的にストレスを感じている人が多く、無意識のうちにその影響が身体に表れることがよくあります。寝ている間に「ギリギリ」という音を立てる人や、起床時に顎の疲れやだるさを感じる人は、ストレス由来の歯ぎしりをしている可能性が高いといえるでしょう。ストレスがかかった状態を自覚していなくても、体はしっかりと反応しており、長期間にわたって歯ぎしりが続くと、歯だけでなく顎や首、肩などにもダメージを蓄積してしまいます。そのため、歯ぎしりの治療には、歯科的アプローチとあわせてストレスケアも並行して行うことが重要です。
・噛み合わせや顎のズレが影響することも
歯ぎしりは心理的な原因だけでなく、口腔内の構造的な要因によって引き起こされることもあります。とくに注意すべきなのが、「噛み合わせ(咬合)」の問題です。上下の歯の当たり方にわずかなズレがあると、顎が安定せず、無意識のうちに歯をすり合わせたり、力を入れて噛みしめてしまうことがあります。また、歯の欠損や詰め物・被せ物が合っていない場合にも、咬合のバランスが崩れ、歯ぎしりの誘因になります。さらに、顎関節の位置が正しくない「顎位異常」や、顎の筋肉に偏りがある場合なども、口腔全体の機能不全から歯ぎしりを引き起こす原因になります。噛み合わせの不調和は、歯科医師による咬合診断や顎関節の評価によって確認され、必要に応じて調整や矯正などの治療が検討されます。ストレスだけでは説明がつかない歯ぎしりには、こうした構造的な要因が隠れていることも多いため、自己判断せずに歯科医院でのチェックが不可欠です。
・習慣・姿勢・睡眠の質も見逃せない要因
歯ぎしりには、日常生活の中に潜む小さな習慣や身体の使い方も深く関わっています。たとえば、頬杖やうつ伏せ寝といった姿勢は、顎の位置に偏りを生じさせ、筋肉や関節へのストレスを生み出す原因となります。また、スマートフォンやPCの長時間使用によって、前傾姿勢が癖になっている方も要注意です。このような姿勢の崩れは、首や肩、顎の筋肉を過度に緊張させ、歯ぎしりを助長する可能性があります。加えて、睡眠の質の低下も大きな要素のひとつです。眠りが浅い、途中で何度も目が覚める、呼吸が浅いといった状態が続くと、身体が十分に休息をとれず、睡眠中の交感神経活動が高まり歯ぎしりが起きやすくなります。また、アルコールやカフェインの摂りすぎ、夜更かしといった生活習慣の乱れも、歯ぎしりの一因とされます。つまり、歯ぎしりを本質的に改善するには、口の中だけでなく、生活全体を見直すことが大切なのです。
歯ぎしりがもたらす口腔内のトラブル

・歯のすり減り・破折のリスク
歯ぎしりによる最大の被害のひとつが、歯そのものへの直接的なダメージです。寝ている間の歯ぎしりでは、日中の咀嚼とは比べものにならないほどの強い力が歯に加わります。この強い摩擦によって、歯の表面(エナメル質)が徐々にすり減っていき、象牙質が露出してしまうことも珍しくありません。歯の咬耗が進行すると、見た目が短くなり、噛み合わせの高さが低下することで顎関節にも悪影響を及ぼす可能性があります。また、強い力が一点に集中することで、歯にヒビが入ったり、場合によっては割れてしまう「歯の破折」につながることもあります。特に神経を抜いた歯や被せ物がしてある歯は脆くなっているため、歯ぎしりによる破折のリスクが高いといえます。このようなダメージは、放置しておくと抜歯に至るケースもあるため、早期発見と予防が非常に重要です。
・歯周病や知覚過敏が悪化することも
歯ぎしりの力は歯そのものだけでなく、歯を支えている歯周組織にも大きな影響を与えます。特に問題となるのが、歯周病の進行を加速させる要因となることです。通常、歯周病はプラーク中の細菌によって歯ぐきや歯槽骨が炎症を起こす疾患ですが、そこに歯ぎしりのような「過剰な咬合力」が加わることで、炎症の部位に物理的なダメージが蓄積され、歯周組織の破壊が進みやすくなるのです。また、歯の表面がすり減ったり、歯根が露出することによって、冷たいものや熱いものに敏感になる知覚過敏の症状も悪化しやすくなります。歯ぎしりを起こしている方の中には、「歯がしみる」「歯ぐきが下がってきた」という訴えがみられることが多く、これらも歯ぎしりが間接的に引き起こしているケースが少なくありません。歯周病や知覚過敏の管理においては、歯ぎしり対策も同時に行うことが、口腔内全体の健康維持に欠かせないポイントとなります。
・被せ物やインプラントが壊れる可能性
歯ぎしりの強い力は天然歯だけでなく、人工的に装着された補綴物にも大きなダメージを与える恐れがあります。たとえば、セラミックの被せ物(クラウン)は審美性と耐久性に優れた材料ではあるものの、横からの強い咬合力に対しては欠けたり割れたりするリスクが少なからず存在します。また、複数本連結されたブリッジの場合には、力が1本の支台歯に集中することで、その歯の根や骨に過剰な負担がかかり、支台歯の寿命を縮める結果につながることもあります。
さらに、インプラント治療を受けている方にとっては、歯ぎしりが致命的なダメージになる可能性もあります。インプラントは顎の骨と直接結合しているため、天然歯のようなクッション性がなく、過度な力を逃がせない構造となっています。そのため、歯ぎしりが続くとインプラント体を支えている骨が炎症を起こし、「インプラント周囲炎」を発症しやすくなり、最悪の場合インプラントの脱落につながることも。高額な治療を無駄にしないためにも、補綴治療を受けている方ほど歯ぎしり対策は必須と言えるでしょう。
顎関節症との関係とは?歯ぎしりが引き起こす顎の異常

・顎の痛みや音の原因になる理由
歯ぎしりは、顎関節や周囲の筋肉に強い負荷を与えるため、顎関節症の引き金や悪化因子になることが多いとされています。特に、就寝中の歯ぎしりでは、何百キロもの力が顎にかかるとされ、その力が一晩中繰り返されることで、関節に大きなストレスがかかります。その結果、朝起きたときに「顎がだるい」「口が開けにくい」「カクカクと音がする」といった症状が現れるようになります。このような音は「クリック音」と呼ばれ、関節内部の関節円板(軟骨組織)がズレることで生じる異音です。これを放置すると、関節円板のズレが悪化し、関節の骨同士が直接こすれ合うようになり、痛みや炎症の原因となります。日中に歯ぎしりや食いしばりの癖がある人は、就寝中と合わせて常に関節が負担を受けている状態であり、顎関節症の発症リスクが非常に高い状態です。初期症状を見逃さず、早期対応が重要です。
・開口障害や噛みづらさにつながる
歯ぎしりの影響で顎関節にトラブルが起こると、口が開きづらくなる「開口障害」や、噛む機能そのものに問題が出るケースもあります。これは関節内部の構造に異常が生じたり、筋肉が過剰に緊張したりすることで、正常な開閉運動が妨げられるためです。「指が2本分しか入らない」「口を開けると痛みが走る」といった症状は、開口障害の典型的なサインといえるでしょう。また、顎関節の動きがスムーズでなくなると、噛み合わせがずれたり、咀嚼時に左右で偏りが生まれたりするため、特定の歯に過度な負荷がかかりやすくなります。これがさらに歯ぎしりや食いしばりを助長するという、悪循環を招くこともあるのです。口を開ける動作は食事や会話に不可欠な動作であるため、顎関節の問題は生活の質(QOL)を大きく左右します。違和感を感じた段階で歯科医院に相談し、関節機能の評価を受けることが大切です。
・放置すると慢性的な障害に発展することも
初期の顎関節症は、顎の動きに伴う軽い音や違和感で始まることが多く、つい「そのうち治るだろう」と放置してしまいがちです。しかし、歯ぎしりを原因とする顎関節へのダメージは蓄積されていくため、何も対策をしないままでは、やがて慢性化し、痛みや機能障害が強くなる可能性があります。慢性の顎関節症になると、口を開けるたびに痛みが出たり、開口量が著しく制限されたりと、日常生活に支障が出るレベルの不具合が生じるようになります。また、痛みをかばうために顎をずらして動かすようになると、顔の左右の筋肉のバランスが崩れ、見た目にも歪みが出ることがあります。さらに、顎の不調が慢性的になることで、首・肩・背中などの全身的な不調に波及するケースも少なくありません。顎関節症は進行すると、元の状態に戻すことが難しくなることがあるため、「顎が鳴る」「疲れる」「痛い」などの軽微な症状が出た段階で、早めの歯科的介入が求められます。
肩こり・頭痛・不眠…全身への影響にも注意

・首や肩の緊張と関連するメカニズム
歯ぎしりがもたらす影響は、口腔内や顎関節だけにとどまりません。無意識に歯を食いしばる習慣があると、咀嚼筋だけでなく、顎から首、肩にかけての筋肉にも過剰な緊張が波及します。特に、側頭筋や咬筋といった噛む動作に関わる筋肉は、首や肩の筋肉とつながっているため、顎に加わる力が首・肩こりの引き金となることがあるのです。こうした筋肉の緊張が慢性化すると、血流が悪くなり、肩が重く感じたり、可動域が制限されてしまうケースも見られます。また、歯ぎしりによって就寝中の体がリラックスできていない場合、日中の疲労感やだるさが抜けにくくなるという悪循環にもつながります。「マッサージをしても肩こりが取れない」「整体に通っても改善しない」といった症状がある方は、歯ぎしりが隠れた原因になっている可能性を疑う必要があります。
・睡眠の質が低下する原因になることも
歯ぎしりの問題は、就寝中に発生することが多いため、睡眠の質に直接的な悪影響を与える可能性が高いとされています。寝ている間に歯ぎしりをしている人は、浅い眠りの時間が長くなり、本来得られるはずの深い睡眠(ノンレム睡眠)が妨げられていることがあるのです。これは脳や身体の十分な休息を妨げる要因となり、朝起きても疲れが取れない、日中に眠気や集中力の低下を感じるといった不調へとつながります。また、睡眠中の歯ぎしりによって顎や顔の筋肉が緊張し続けるため、寝ているのに全身がリラックスできていない状態が続くことになります。さらには、歯ぎしりの音が大きい人では、同室で寝ている家族の眠りを妨げてしまうこともあります。このように、歯ぎしりは本人だけでなく、周囲にも悪影響を及ぼす「見えにくい睡眠障害」の一種と考えることができ、軽視してはいけません。
・自律神経の乱れと悪循環
歯ぎしりが継続することで起こる全身症状の背景には、「自律神経の乱れ」が深く関係しているケースもあります。ストレスや疲労、睡眠不足などが原因で交感神経が優位になると、筋肉の緊張が高まり、歯ぎしりが悪化します。そして、その歯ぎしりがさらに睡眠の質を下げ、疲れが取れないまま次の日を迎えるという悪循環が形成されてしまうのです。自律神経は全身の臓器やホルモンバランスを調整する役割を担っており、これが乱れることで、頭痛・肩こり・不眠・イライラ・胃腸の不調など、様々な不定愁訴が現れることがあります。つまり、歯ぎしりは単なる「癖」や「歯の問題」ではなく、体全体のバランスに関わる重要なサインと捉えることが大切です。慢性的な不調に悩んでいる方こそ、一度歯ぎしりの有無を見直し、必要であれば歯科での精密検査を受けることをおすすめします。
歯ぎしりに気づくきっかけとセルフチェック

・朝起きたときの顎の疲れや違和感
歯ぎしりに悩む方の多くは、自分が歯ぎしりをしていることに気づいていません。それは、歯ぎしりが多くの場合、就寝中の無意識な行動として起こるからです。しかし、朝起きたときに「顎がだるい」「こわばっている感じがする」「口を開けると違和感がある」といった症状がある場合、それは歯ぎしりのサインである可能性が高いです。とくに、朝から頭が重い、肩や首に張りを感じるという人は、寝ている間に顎の筋肉を使い続けたことによる筋肉疲労かもしれません。これらの違和感は、日中には徐々に改善することもありますが、繰り返し起こるようであれば要注意です。さらに進行すると、顎関節症のリスクも高まりますので、「なんとなく変だな」と感じたら、歯科での相談をおすすめします。朝の不調は、就寝中の歯ぎしりを知らせる大切な警告サインなのです。
・パートナーから指摘される「音」
歯ぎしりが音を伴うタイプである場合、周囲の人の指摘によって気づくケースも多くあります。特に、「寝ているときにギリギリ音がする」「歯をカチカチ鳴らしている」など、寝室を共にする家族やパートナーから教えてもらって初めて自覚するという人が非常に多いです。自分では熟睡しているつもりでも、実は寝ている間に強く歯をこすり合わせており、それが大きな音となって現れているのです。このような音は、グラインディング(歯を左右にすり合わせる)やタッピング(カチカチと打ち鳴らす)といったタイプの歯ぎしりでよく見られます。本人にとっては無音で行われていると思いがちですが、外部にはっきりと聞こえるほどの強い力が加わっている証拠でもあり、放置すべきではありません。就寝中の歯ぎしりは、本人が認識しにくい分、家族からの客観的な視点が非常に重要です。指摘された場合には、その声をきっかけに受診を検討しましょう。
・歯の形の変化や詰め物の脱落で気づく
日常生活の中で、歯の変化を感じたことはありませんか?歯ぎしりによって起こるもう一つの分かりやすいサインが、「歯の見た目や状態の変化」です。たとえば、「前よりも歯が平らになってきた」「歯の先が欠けている」「詰め物が何度も取れてしまう」などは、歯ぎしりによる力の蓄積によって引き起こされている可能性が高い症状です。特に、詰め物や被せ物がしっかり合っていたはずなのに突然外れてしまった場合、それは単なる接着不良ではなく、歯ぎしりによる繰り返しの衝撃が原因であることが少なくありません。また、鏡で歯を見たときに「昔より短くなった気がする」と感じた場合、それはすり減りの兆候かもしれません。こうした視覚的な変化や繰り返す補綴物のトラブルは、口腔内で起きている異常を知らせる「静かな警告」です。自分では気づきにくい歯ぎしりも、こうした小さな変化に目を向けることで発見できる場合があります。
歯科で行う歯ぎしりの診断と検査内容

・咬合診査や顎の可動域のチェック
歯ぎしりの診断には、視診だけではなく、顎や噛み合わせの機能を総合的に評価する検査が必要です。初診時にはまず、歯科医師が口腔内を確認し、歯の摩耗や詰め物の破損、歯ぐきの状態などを視診します。次に行うのが「咬合診査(こうごうしんさ)」です。これは、上下の歯がどのように噛み合っているかを確認する検査で、咬み合わせのズレや強く当たっている部分(早期接触)がないかをチェックします。加えて、顎の可動域(口の開閉動作)や、開け閉めのスムーズさ、顎関節に痛みや異音がないかなども重要なポイントです。患者自身が気づいていなくても、顎の可動域に左右差がある場合や、開閉時にクリック音(カクンという音)がすることもあり、これらは歯ぎしりや顎関節症の兆候として見逃せません。これらの検査結果をもとに、必要であれば咬合調整や補綴物の見直しを行うことで、歯や顎への負担を軽減し、症状の改善を図ることができます。
・歯の摩耗や咬耗の状態確認
歯ぎしりの診断において、歯の表面の変化を見逃さないことが極めて重要です。歯科医師は、歯の「咬耗(こうもう)」や「摩耗(まもう)」の状態を詳細に観察します。咬耗とは、噛む動作や歯ぎしりによって歯がすり減る現象で、主に噛み合わせの面に生じます。これに対し、摩耗は歯磨きの仕方や習慣的な癖(例:噛みしめや食いしばり)によって歯の側面などに起こります。歯ぎしりによる咬耗は、通常の咀嚼よりも数倍の力がかかるため、短期間で著しいすり減りが生じることもあります。さらに、咬耗が進行すると象牙質が露出し、知覚過敏や歯髄への刺激を引き起こすこともあります。また、被せ物や詰め物の破損が頻繁に起こる場合にも、その裏にある咬合力の異常が疑われます。診断の際には、過去の記録やレントゲン画像と現在の状態を比較し、歯の変化を時系列で確認することで、歯ぎしりの影響を明確に評価することが可能です。患者が気づいていないダメージを的確に拾い上げることが、早期対処につながります。
・必要に応じてマウスピース治療の適応判断
歯科医院での検査の結果、歯ぎしりが疑われる場合には、ナイトガード(マウスピース)治療の適応が検討されます。ナイトガードは、就寝中に上下の歯が接触しないようにすることで、歯や顎関節への過度な負担を軽減する装置です。歯ぎしりの種類や強さ、歯の状態に応じて、ハードタイプ・ソフトタイプなどの素材や形状が使い分けられます。歯科医師は、噛み合わせや顎の動きを考慮した上で、患者に合ったナイトガードを設計し、型取りをして作製します。装着感や違和感がないように、細かく調整を重ねながら完成させていきます。マウスピース治療は、歯ぎしりそのものを止めるものではありませんが、歯や補綴物を守り、症状の進行を抑える効果が非常に高いとされています。必要に応じて保険が適用される場合もあるため、費用面が気になる方も安心して相談できます。歯ぎしりが疑われる際には、マウスピースの適応を含めたトータルな評価と治療方針の立案が不可欠です。
ナイトガード(マウスピース)による対処法

・歯を守るクッションの役割とは
ナイトガード(マウスピース)は、歯ぎしりによる歯や顎へのダメージを軽減するための重要な装置です。特に、就寝中の歯ぎしり(睡眠時ブラキシズム)は本人の意思とは無関係に発生するため、自分で制御するのは困難です。そこで、上下の歯が直接接触しないように間にクッションとなるマウスピースを装着することで、咬合力の分散や歯の摩耗の防止を図ります。歯ぎしりによって最もダメージを受けるのは、歯の咬合面(噛む面)と顎関節ですが、ナイトガードを使用することで、これらの組織を物理的に保護することができます。ナイトガードの材質は主に硬質レジン(ハードタイプ)や軟質シリコン(ソフトタイプ)があり、患者の咬合状態や症状に応じて選択されます。歯ぎしりが強い人や、歯の破折歴がある方には、耐久性のあるハードタイプが用いられることが多く、一方で装着感を重視する方にはソフトタイプが適しています。マウスピースは、あくまで“歯ぎしりの力を和らげる装置”であり、根本的な原因の解消には別途アプローチが必要です。
・顎関節の保護と筋肉の緊張緩和
歯ぎしりによって影響を受けるのは歯だけではありません。顎関節やその周囲の筋肉も常に大きな負荷を受けているため、痛みや不快感の原因となることがあります。ナイトガードの使用は、これらの筋肉や関節の負担を軽減する目的でも有効です。装着することで上下の歯が直接接触することがなくなるため、無意識の噛みしめやこすり合わせる動作が抑えられ、顎の動きを一定の範囲に制御する効果が期待できます。その結果、咬筋や側頭筋といった筋肉の緊張が和らぎ、顎のだるさや痛みが緩和されるケースも少なくありません。また、顎の位置が安定することで、関節への負担も軽減され、顎関節症の予防や症状の改善にもつながるとされています。特に、朝起きたときに顎が痛い・開けにくいという方は、ナイトガードを使うことで日常生活の快適さを大きく改善できる可能性があります。歯や関節、筋肉を守る“予防装置”として、ナイトガードは歯ぎしり対策の基本アイテムといえるでしょう。
・保険適用になる場合と費用の目安
ナイトガード治療は自費診療と思われがちですが、症状に基づいた明確な診断があれば、健康保険の適用対象となることがあります。たとえば、「睡眠時ブラキシズムによる歯の咬耗」や「顎関節症に伴う顎の痛み」などが確認された場合、保険適用でナイトガードを作製することが可能です。この場合の自己負担費用は、医院や地域によって若干の差がありますが、おおむね3割負担で5,000~7,000円程度が目安です。一方、審美性や快適性、精度の高い素材を重視した自費のナイトガードは、1万円〜3万円程度になることもあります。自費治療では、細かな噛み合わせの調整や装着感への配慮がより丁寧に行われる傾向にあり、長期的な使用を前提とする場合にはおすすめです。いずれのケースでも、ナイトガードは「一度作れば終わり」ではなく、定期的な調整や交換が必要になることもあるため、歯科医院での定期的なチェックを継続することが大切です。費用の面が不安な方は、受診前に保険適用の可否や料金体系について医院に相談するとよいでしょう。
歯ぎしりを軽減するための日常習慣

・ストレスマネジメントとリラックス法
歯ぎしりの大きな原因のひとつが「ストレス」であることは多くの研究で明らかになっています。ストレスが溜まると、交感神経が優位になり、無意識に歯を食いしばったり、寝ている間に歯ぎしりをしたりする傾向が高まります。そのため、日常生活の中でストレスを上手に解消することが歯ぎしりの予防・軽減に直結します。具体的には、ゆっくり湯船に浸かる、深呼吸をする、アロマや音楽を使って気分を落ち着けるなど、副交感神経を優位にする時間を意識的に持つことが効果的です。また、趣味や運動、十分な睡眠など、自分なりのリラックス法を日常に取り入れることも有効です。精神的な緊張が続いている状態では、どんなに歯科的な対処をしても再発しやすいため、“心のケア”も歯ぎしり改善には欠かせない要素と言えるでしょう。ストレスは無自覚に蓄積していることも多いため、意識的に「自分を緩める習慣」を作ることが大切です。
・姿勢の見直しと就寝環境の改善
日常の何気ない姿勢が、歯ぎしりを助長する原因になっていることがあります。たとえば、長時間のスマホ使用やデスクワークによって猫背や前傾姿勢が習慣化すると、顎や咀嚼筋に偏った負担がかかり、無意識に食いしばる癖がつきやすくなります。また、頬杖やうつ伏せ寝といった不安定な姿勢も、噛み合わせや顎の動きに悪影響を及ぼします。こうした姿勢のクセは、日中の歯ぎしり(覚醒時ブラキシズム)を引き起こす原因となることがあるため、こまめな姿勢のチェックやストレッチ、適度な休憩が大切です。加えて、寝具や枕が合っていない場合も、顎のずれや筋肉の緊張につながりやすくなります。高さが合わない枕で眠ると、首や顎に不自然な角度が加わり、寝ている間に歯を食いしばる要因にもなるのです。快適な睡眠環境を整えることで、身体全体がリラックスしやすくなり、就寝中の歯ぎしりを軽減する手助けとなります。
・食いしばりを防ぐ日中の意識づけ
歯ぎしりと似た現象に「食いしばり(クレンチング)」があります。これは日中、無意識のうちに上下の歯を強く噛みしめてしまう癖で、デスクワーク中や運転、スポーツ中、集中しているときなどに起こりやすいとされています。特に、仕事中のストレスや緊張が高い人ほど、知らず知らずのうちに食いしばっていることが多く、これが顎関節や歯、筋肉への慢性的な負担となって蓄積していきます。このような食いしばりを防ぐには、「上下の歯は離しておくのが正常な状態」という意識を持つことが大切です。実際、リラックスしているときには上下の歯は触れていないのが正常です。付箋に「歯を離す」と書いてPC画面に貼る、スマホの待ち受けに設定するなど、視覚的なリマインダーを活用することで、意識的に歯を離す習慣が身に付きます。また、口を軽く開けて深呼吸するだけでも咀嚼筋の緊張を緩めることができるため、定期的に行うと効果的です。日中の小さな意識づけの積み重ねが、夜間の歯ぎしり軽減にもつながると考えられています。
歯ぎしりが気になるなら、まずは歯科で相談を

・放置するリスクと早期対応の大切さ
歯ぎしりは一見、ただの癖や寝相の一種のように思われがちですが、放置することで歯・顎・全身に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、決して軽視すべきではありません。強い咬合力による歯の摩耗や破折、詰め物の脱落だけでなく、顎関節症や肩こり、頭痛、睡眠障害など、多岐にわたる不調の引き金になることが知られています。さらに、歯周病が進行している場合は、歯ぎしりによる咬合性外傷が加わることで歯の喪失リスクが大幅に上がることもあります。多くの人が「音がしないから問題ない」「痛みがないから大丈夫」と見過ごしがちですが、無自覚であっても歯ぎしりは進行し、取り返しのつかない結果につながることもあるのです。だからこそ、気になる症状があれば早めの受診が重要です。早期の段階であれば、ナイトガードや咬合調整などの比較的簡単な処置で症状の進行を防ぐことができます。
・専門的なアプローチで根本的な改善へ
歯ぎしりの根本的な改善には、症状の原因を正確に特定し、それに応じた治療方針を立てることが必要不可欠です。歯科医院では、視診や咬合診査、筋肉・顎関節の状態を含めた総合的な検査を行い、患者一人ひとりに合ったアプローチを提案します。たとえば、咬み合わせが原因であれば咬合調整や補綴物の見直し、筋肉の緊張が強い場合にはマウスピースによる保護と緊張緩和、ストレスが主因であれば、生活習慣の改善やリラックス法の指導が行われることもあります。また、歯ぎしりと顎関節症が併発しているケースでは、顎の動きを安定させるためのスプリント療法なども検討されます。こうした多角的な治療により、ただ症状を抑えるだけでなく、原因から改善して再発を防ぐことが可能になります。市販のマウスピースで済ませようとせず、専門的な診断と継続的な管理を受けることが長期的な健康の鍵です。
・自分に合った予防と対策で歯と体を守る
歯ぎしりは一人ひとりの生活スタイルや体質によって原因や影響が異なります。だからこそ、自分に合った予防と対策を見つけることが、歯と体の健康を守るために重要です。歯科医院では、ナイトガードによる保護だけでなく、咀嚼筋の過緊張を抑えるためのストレッチやマッサージの指導、日中の食いしばりを抑えるための行動療法(TCH是正)など、幅広いアプローチを受けることができます。また、睡眠環境の見直しや姿勢の改善、食事内容の調整など、生活全体に目を向けることも歯ぎしり予防に効果的です。歯ぎしりは日々の積み重ねによって進行するため、セルフケアと歯科でのプロケアを両立させることがポイントです。特に、被せ物が多い人、インプラント治療を受けている人、矯正中の人は歯ぎしりの影響を受けやすいため、定期的なチェックとメンテナンスが欠かせません。「なんとなく気になる」で済ませず、今このタイミングで行動を起こすことが、将来の大きなリスクを回避する第一歩になります。
監修:青山一丁目 麻布歯科
所在地〒:東京都港区赤坂8-5-32 田中駒ビル1F
電話番号☎:03-6434-9877
*監修者
青山一丁目 麻布歯科
ドクター 安達 英一
*出身大学
日本大学歯学部
*経歴
・日本大学歯学部付属歯科病院 勤務
・東京都式根島歯科診療所 勤務
・長崎県澤本歯科医院 勤務
・医療法人社団東杏会丸ビル歯科 勤務
・愛育クリニック麻布歯科ユニット 開設
・愛育幼稚園 校医
・愛育養護学校 校医
・青山一丁目麻布歯科 開設
・区立西麻布保育園 園医
*所属
・日本歯科医師会
・東京都歯科医師会
・東京都港区麻布赤坂歯科医師会
・日本歯周病学会
・日本小児歯科学会
・日本歯科審美学会
・日本口腔インプラント学会
投稿日:2025年3月27日